Aさんもまた、中学の友達と関わりはあったものの、通信制の高校に進学する友人がおらず、孤立してしまう不安がありました。
人とのつながりや情報がほしいという思いと、「アソシア」の雰囲気にひかれ、通うことを決めました。
▽Aさん(16)
「同い年としか関わってなかったし、学校がいやになった原因も同い年が多かったので、年上の方が性格に合うのかな、みたいな」
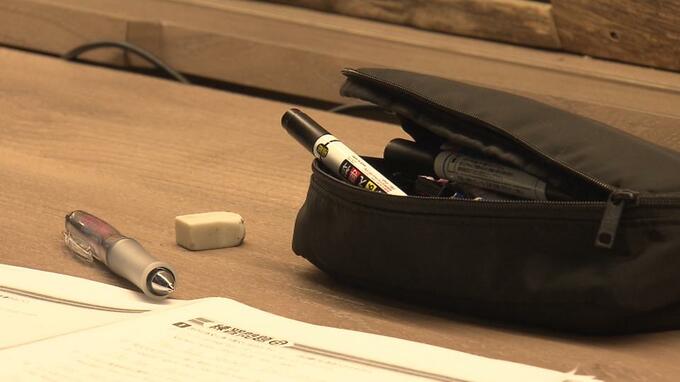
ここでの1日は、朝の送迎に始まり、学習やキャリア形成のサポートまで。社会福祉士などの資格を持った職員が、10代を支援しています。
▽Aさん(16)
「最初は慣れるまでは休み休み通っていたんですけど、送迎もやってくれるのもあるし、プログラム自体が楽しいことが多いので、そこまでストレスになることがないからよく来てる感じ」
「人と関われているというのもあるし、来てなかったら自己理解とかも出来てなかっただろうから」
「(今まで)悩むことが多かったから、そういうも生かせたらなと思って、心理系の大学とか、学べるところに行けたらなって思います」
現在、県の貧困対策事業で運営される支援施設はおよそ200か所。
そのうち、自立支援を必要とする「15歳以上」に特化した施設は数か所ほどで、
県が重点的に進めた小中学生の貧困対策に比べ、受けられる支援は手薄になっています。
▽アソシア 津嘉山拡大さん
「15っていう年齢を境に、高校に通わない子への支援はぐっと狭くなる。支援が行き届いていない、制度の間の子どもたちがいる 」

こうした「15歳以上への支援」は、小中学生を支える人たちの善意に頼る部分が大きいのが現状だといいます。
▽アソシア 津嘉山拡大さん
「元々支援領域が中学校まで、対象年齢が中学校までであるにも関わらず、中学校のときの支援者さんがどうにか、ボランティア的な活動でその子に関わり続けて自立を支援している状態」
「ボランティアでなくて、青少年を支える仕組みづくりが必要です」
<記者MEMO>
津嘉山さんによると、こうした“青少年”の「自立支援」の動きは全国では先駆的な取り組み。これまで支援が行き届いていなかった人は多く、15歳以上を対象にする支援施設には問い合わせが非常に多いといいます。
しかし特定の資格を持った職員の人手不足など、支援の拡充には課題が多いのも確かです。「誰一人取り残さない社会」の実現に向けた社会の努力が問われています。








