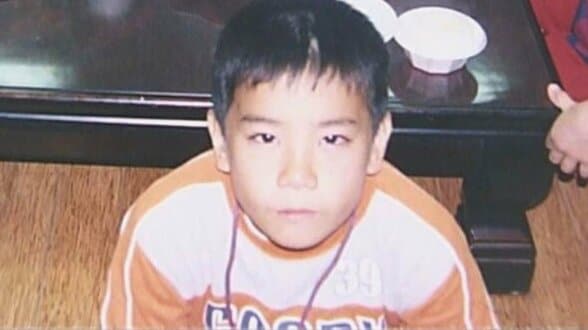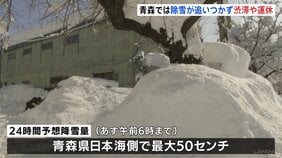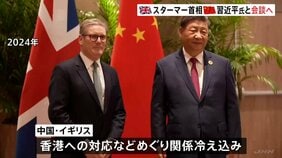対策が進みにくいもう1つの背景は農家の高齢化、後継者不在という問題だ。
「あと10年、農家としてやるか微妙だと、そういう農家さんに対策を強制的に進めるべきかというと、僕は進めるべきじゃないと思います。そこも難しい問題」
子牛を送り出す繁殖農家は、一定の割合の発症を割り切って経営を続け、陰性か陽性か分からない牛を出荷することはできる。しかし牛を購入する側の理屈は異なると目堅准教授は指摘する。
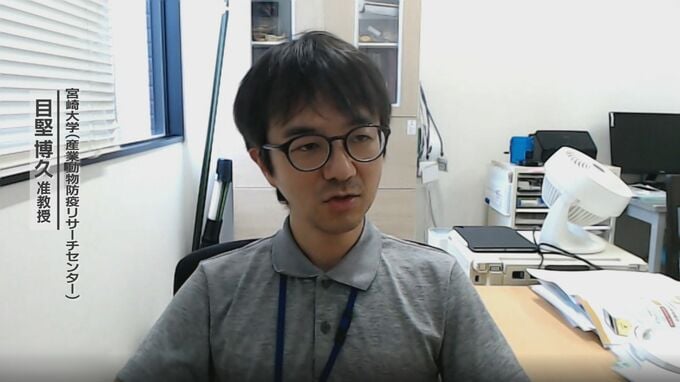
「肥育農家さんからしたら、70万円で買ってきて、餌をあげて120万円で売ろうとしていると。120万円の牛が発症したらゼロになるんで、それはとてもじゃないけど受け入れられる問題じゃないんですね」
「県外の肥育農家さんは何を考えるかというと、“ウイルス対策をしている別の市場から買おう” となってきてしまう。(まん延状態が続くことは)沖縄県全体の繁殖農家からしたらあまりよろしくないことですよね。遅れれば遅れるほど対策は難しくなるので、やるなら早い方がいい」
<取材後記>
県内で牛伝染性リンパ腫の対策が遅れる背景には、「対策ができない病気だ」という思い込みがあると感じた。牛のリスクに応じた隔離の工夫などで対策が進み、ほとんど感染牛を出していない地域は宮崎県などにある。
宮崎大学の目堅准教授は、沖縄でも感染率が低い小さな地域を作り、そのメリットを周りの農家さんたちも実感できれば、そこから徐々に対策が拡大していくとして、着実な取り組みが望ましいと話している。(取材 久田友也)