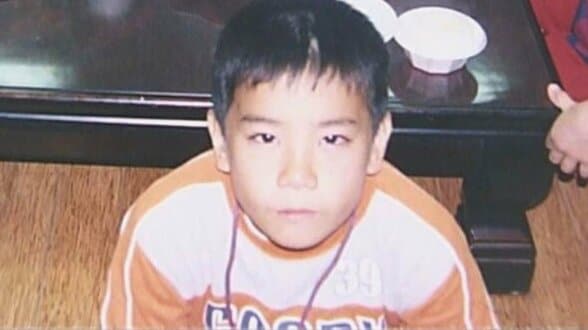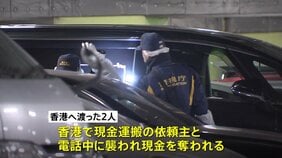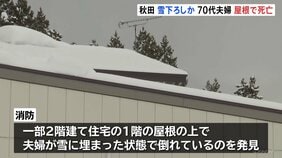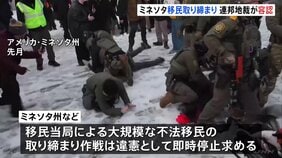被災後に大量に必要となる仮設住宅が、安全で使いやすい土地に建てられるとは限らない。稲垣さんは、能登と土地の条件が似た沖縄だからこそ、災害時の仮設住宅についてどんな課題があるのかを知り、想定しておいてほしいと訴える。

「仮に平坦な土地を求めて田畑を借りて応急的に仮設住宅を作るとしても、上下水道など住宅建設の基礎が近くにないとすぐに建設はできないので、事実上、転用は難しい。特に下水道は本管が近くを通っていなかったら難しい」
「仮に転用しても、過去の大災害を見ても、2年、3年では帰ってこない(仮設住宅暮らしが長期化する)。そうなると、その後田畑として機能することも難しくなる」

また土地を見つけられても、住み慣れた土地から遠くなると、地域の繋がりがなく孤立しがちになる。公共交通の体制がぜい弱であれば、通勤通学・通院・買い物などの行動が難しくなるなど、被災後に暮らしを立て直す仮設住宅について考えておくべきことは多いという。
稲垣さんがこれだけ仮設住宅についての備えを説くのは、阪神淡路大震災の経験、東日本大震災の「被災後」を見届けてきたからだ。