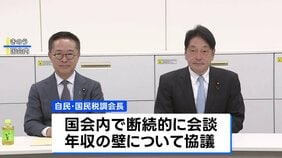豪雨被害拡大の背景に 元日の地震ー
「さらに9月に感じたことは、地震で護岸が沈んでいるところが多かった。例えば珠洲市の鵜飼地区というところにある鵜飼川のほとり、大谷地区の珠洲大谷川を歩くと、土手が下がっているんですね。何を見て分かったかというと、「橋」です。橋が浮いた感じになってて。周りは落ちてる、そんな感じだったんですよね」
こうした被災状況にあった能登半島に、9月21日から22日にかけての豪雨が襲った。
1時間雨量121ミリ。3時間で222ミリ、24時間雨量412ミリ、22日午後4時までの48時間雨量は輪島市で498. 5ミリ、珠洲市で393.5ミリに上る、観測史上最大の雨が降った(輪島市)。

これによって、氾濫した河川は23河川(珠洲市で7、輪島市で6、能登町3、 七尾市5、志賀町2)。16日現在、7つの市と町で死者は14人(行方不明者1人)に上った。
「(奥能登豪雨は)桁違いの雨だったけど、はん濫した原因は沖縄と同じ、狭くて短い川。あっという間に処理能力を超える雨が降ってしまった」
「沖縄には大きな川がないから洪水は起こりにくいという人は結構いるんですけども、違うわけですね。むしろ短い川だから処理できなくてあふれてしまう」
地震被災後の仮設住宅を襲った雨災害
また稲垣さんは今回の豪雨災害で、地震後に設置された「仮設住宅」が被災した状況にも注目している。
能登半島地震を受け、石川県内に6518戸の仮設住宅が建設されている(既存の建物の借り上げを除く・10月15日時点)が、このうち輪島市と珠洲市で約200戸が床上浸水の被害にあった。稲垣さんはこのうち142戸が床上浸水した「宅田町第2団地」を、豪雨被災前に訪れていた。