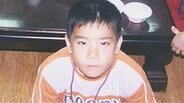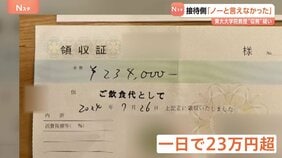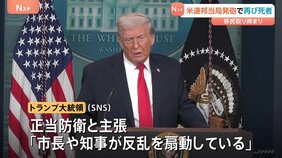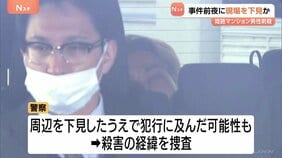今回の訪問先に保守系シンクタンク(政策研究機関)が含まれたことについては、政治任用という形で政府の重要ポストに任命される人材も多いシンクタンクへのアプローチは、沖縄を理解してもらうための土壌を作るうえで重要だとも指摘した。
また今回玉城知事の面会相手には、政府与党である民主党の議員補佐官や政策立案担当もいるが、彼らも重要な役割を担っている。
連邦議会の補佐官は、議会内の立法手続きにおける役割の大きさから「選出されていない議員」とも言われる。

前嶋教授によると、連邦議会では上院・下院ともに、1人の議員に対して複数人の補佐官がつく。
立法の実務を行い決議を書いたりと幅広い役割を担うことや、ワシントンのなかで政治キャリアを積み上げていくことが多いことから、“補佐官”といっても、沖縄の今後を見据えるうえで政治人脈の1人になると考えられるという。
訪米の目に見える“成果”は簡単には見えてこない現状だが、継続したアプローチが重要となる。
沖縄県知事として初めて訪米した西銘知事も「沖縄の基地負担軽減」と、「米兵の綱紀粛正」を求めていた。
それから39年たった現在も、沖縄は同じ負担を抱え、県知事から変わらぬ要望が上がる。これだけ継続的に直接訪米に取り組まざるを得ない沖縄の現実に、日米両政府は真剣に向き合い、答えるべきだ。