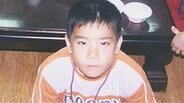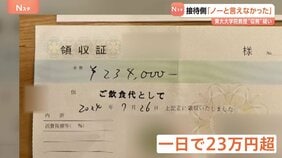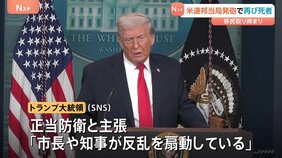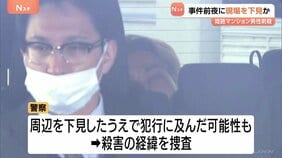しかし2015年の翁長知事の訪米からは、それまで国務長官などトップ対応だった面談相手が、官僚にすぎない「日本部長」以下に止まるようになり、“冷遇”といえる状況が定着しており、今回の玉城知事も、国務省・国防総省とも日本部長との面談となった。
沖縄の現状を直接米国に訴えるために続いてきた知事訪米だが、近年はその成果を疑問視する厳しい声があることも確か。今回の知事訪米の評価を有識者に聞いた。
▽上智大 前嶋和弘教授(現代アメリカ政治・外交)
「沖縄と日本政府の関係について、“日本政府がうまくまとめていてくれる”という意識が、どうもワシントンで強くなっている」

現代アメリカ政治や外交に詳しい、上智大学の前嶋教授は、過去に比べ冷遇とみえる近年の米側の対応の背景には、日米の軍事的一体化が進む中で、沖縄の声が届きにくくなっている現状があると分析する。
政府と別の動きをする知事の訴えは“不協和音”に聞こえる
「安全保障上、日本の重要性はとても高くなっていて、沖縄の重要性はとても高くなっている」「日本と米国は同じ方向性にいるんだというのが、米国の中でもかなり強く信じられている。その中で(知事訪米のような)別の動きがあるとそれは不協和音に聞こえてしまう。そうじゃないんですけども。そういうところは、やっぱり沖縄の声がなかなか伝わっていかない理由のひとつ」
前嶋教授はこうした状況の中で沖縄県知事が訪米することには、意味があると評価する。
「(知事が)短い時間の中でお会いになられた方は、それなりの活動をしてる方だと見受けられます。(沖縄からの)声は常に上げていく必要があって、今回の玉城知事の訪米はそこが目的だと思いますし、1人ひとりワシントンの中心の人たちに会っていくことは重要」

前嶋教授は、伝えることを止めてしまえば沖縄の人たちの意見が米国に全く伝わらなくなると話した。