「こんにちは訪問看護ステーションエイトです」
「よろしくお願いします」
宜野湾市に住むゆりこさん。去年8月長女のゆずはちゃんを出産しました。
「すごいできたー!上手になったね」
この日、自宅を訪れたのは助産師の喜久山仁美さん。

喜久山さん「どう発達?どこまでいけてる?」
ゆりこさん「今寝返りしてくるくる回ってという感じで、まだずりばいまではいけてないんですけど腹ばいで方向転換したりとか」
ゆりこさんは妊娠34週のとき1382グラムでゆずはちゃんを出産。妊娠中にゆずはちゃんの腸閉塞が分かり、生まれてすぐに手術を受けなれけばなりませんでした。手術後、新生児治療室(NICU)に入ったゆずはちゃんは、2か月半後にようやく退院することができました。
ゆりこさん
「生まれたらすぐに手術をしないといけないという不安もあるし、まずちゃんと元気に生まれてきてくれるかなという不安ももちろんあって。不安はいっぱいありました」
宜野湾市にある訪問看護ステーションエイト。去年5月に開所し、県内12市町村を対象に精神や母子支援に特化した訪問看護を行っています。
訪問介護ステーションエイト 喜久山敦所長
「僕が精神科認定看護師としてライセンスを持っていて、嫁が助産師としてやっていたのでそこでコラボして訪問の形で出来る事はないかと考えたのが、うちのステーションの始まりです」
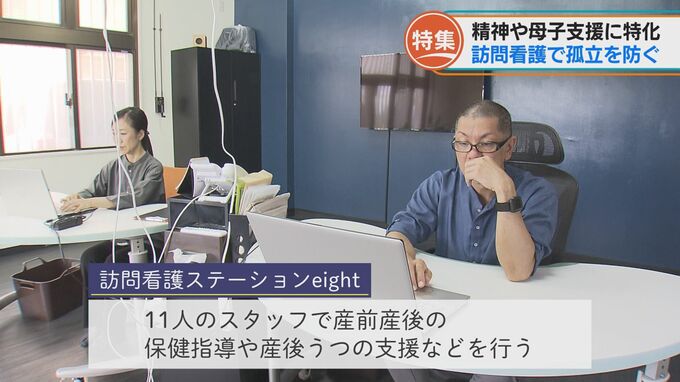
精神や母子支援に特化した訪問看護は全国的にも珍しく、県内では初めてとなるこちらの施設。精神科認定看護師で所長の喜久山敦さんと、妻で助産師の喜久山仁美さんが中心となり現在11人のスタッフで産前産後の保健指導や産後うつの支援などを行っています。
喜久山さんは、コロナ禍で不安を抱える妊婦が増えてきていると感じています。
喜久山仁美さん
「コロナ禍になって病院の母親学級とかかなり減ってきている。もしくはお休みになっている。そういうところで妊娠中の教育が十分でないまま不安なままお産をする。そしてお産も立ち合い出産が今できない状態なので不安なまま生んで不安なまま子育てがスタートするというところでコロナ禍で産後うつは増えているんじゃないかなと感じている」
日本産婦人科医会によると出産した母親の約10人に1人が「産後うつ」になると言われています。また今年3月に全国の分娩を扱う医療機関に行ったアンケートによると、出産時の立会いや産後の家族の面会を中止した医療機関が6割を超えていたことが分かりました。
精神科医で産婦人科医としての経験も持つオリブ山病院の宮貴子医師は、孤立を防ぐためにもまずは話を聞いてくれる“受け皿”を増やす必要があると話します。
オリブ山病院 宮貴子医師
「精神科の病院もクリニックもかなりいっぱいいっぱいで、コロナもありますけど周産期に関わらず精神科の患者さん自身が多いので新規の患者さんを見てく中でどうしても待ちという状況が出てきます」
「ゆっくり話を聞いてくれる場所というのが精神科に来る前にもう一つワンクッションあるときっと患者さんも患者さんと呼ばれずにすんだんじゃないかなと思うことはあります」
そのうえで、声を挙げることをためらわないで欲しいと呼びかけます。
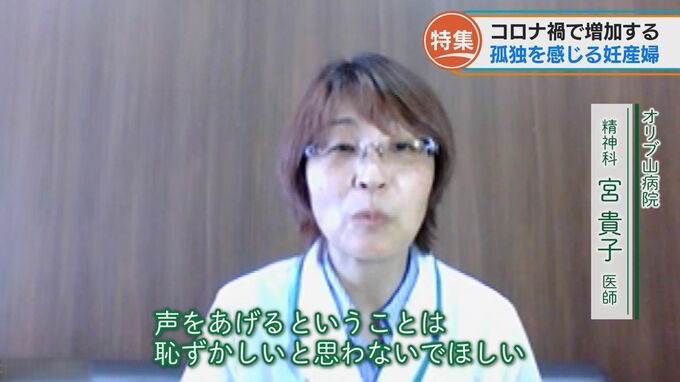
宮貴子医師
「自分にはもうこれ以上は無理と思ったときにはどこかに繋がるというか」
「産科のクリニックであるとかそういったところに声を挙げていただければじゃあここに繋ごうかというのは案内していただけると思うので、声を挙げるということは恥ずかしいとは思わないでいただきたい」
訪問看護ステーションエイトの喜久山さんは「訪問看護をもっと身近に感じて欲しい」と話します。
喜久山さん
「利用者さんがよく言われるのは訪問看護は敷居が高い。どんなシステムかわからないからSOSを出しずらいとか、もっと私より困っている人がいるからSOSできないという声を聞くことが多い。困っていることがあればまずは当ステーション、もしくは地域の保健師さんにどなたでもいいので困っていることを伝えて欲しい」

訪問介護を利用するゆりこさん
「家族とか親戚以外に地域にこうやって味方してくれる方がいるのはすごく心強い」
「同じような立場で早産児を出産した親御さんや双子ちゃんのパパママは大変なことや心配事が特に多いと思うんですけど、こういうとっても素敵な制度があるので是非利用して一緒に楽しく子育てできたらいいなと思います」
不安を抱える妊産婦を孤立させないために。その声を聞く場所が必要とされています。








