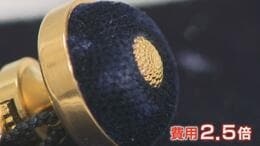差出人のないハガキに託された願い
入隊後どこの戦地に赴くか、家族にすら言ってはいけなかったという。箱石さんも、二郎さんがいつどこに向かうのか知らなかった。
面会の翌日、差出人の名前がなく「新宿1230通過」とだけ書かれたハガキが届いた。文字を見て、すぐに夫の字だとわかった。赤ちゃんを背負って新宿駅に急ぎ向かおうとした。でも、大混雑のバスに乗り込むことができず、間に合わなかった。
「夫はきっと、トイレか何かに隠れて必死にハガキを書いてくれたのだと思います。汽車の窓から外を見て、私と子どもがどこにいるか探したと思います。家族の姿がない新宿駅を通過したとき、夫はどんな気持ちだっただろう…」と箱石さんは言葉を詰まらせた。
「最後に一目、子どもを見たい」というささやかな夫の願いを、かなえてあげられなかった。後悔は、107歳になる今も頭から離れない。

栃木県の実家の父親から「東京は危ないから早く子どもを連れて逃げてきなさい」と繰り返し催促され、店を閉めて疎開した。その数日後、大空襲で東京は焼け野原になった。箱石さん夫婦の理容店も住んでいた家も、跡形もなく焼けてしまった。
ふるさとで親戚の家に身を寄せながら、1945年8月、終戦を迎えた。
しかし、夫・二郎さんに関する知らせは何もなかった。どうやら満州に赴いたようだったが、生きているのか亡くなったのかもわからない。ただただ帰りを待った。
「また家族4人で一緒に暮らしたい」「小さくてもいいから、夫婦で理容店を開きたい」。
二郎さんとの再会を待ちわびながら、戦後の混乱期を子ども2人と生活していかなければならなかった。あす食べるものはどうするのか。1日1日をどうにか暮らしていく日々が続き、気づけば終戦から何年もの月日が流れていた。