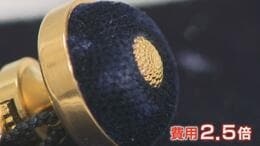夫の戦死「夢も希望もなくなった」

1953年、終戦から8年が経ったある日突然、二郎さんの戦死の公報が届いた。呆然とする暇もなく、遺骨受領があると東京に呼ばれて向かった。白い遺骨が入っていると思われる箱を手渡された。息子が箱を持ったまま転びそうになったとき、箱のなかで、カラカラと音がした。
「お母さん、これお骨じゃないよ!」
息子にそう言われて箱を開けると、小さな位牌が入っていた。遺骨ではなく、ただの板切れだった。

二郎さんが家を発ったとき生後10か月だった息子は、小学校3年生になっていた。記憶に残っていない父の姿を思い描き、対面できる日を夢見ていた。「ずっと待っていたのに、こんな板切れだ」と息子は泣いた。
箱石さんは、「骨も爪も髪の毛も何もない。爪だけでもいいから本物が欲しかった」と悔しさをにじませた。
「これからどうして生きていこう。夢も希望もなくなった」。
4~5日雨戸を閉めて、暗い家のなかで考えた。もし自分が倒れたら、幼い子どもたちはどうして食べていくのか。実家や親せきの世話になりっぱなしというわけにもいくまい。子どもに苦労かけるのもかわいそうだ。途方に暮れた。

娘に「お父さんのところに一緒に行こう」と伝えた。娘は「お父さんのところに行くということは、死ぬんでしょ?」とたずねる。「そうだよ」と答え、抱き合った。
そこへ、息子が外遊びから戻ってきた。「どうしてこんなに家の中は真っ暗なの?」
「お父さんのところに、お姉ちゃんと一緒に3人で行ってしまおう」と伝えた。

「いやだよ!おれ、死ぬの嫌だよ!」と言って息子は駆け出していった。
近くに住む甥が駆けつけてきて「おばさん、なんてことするんだ。子どもたちには夢も希望もあるんだ、こんなことをしても、おじさん(二郎さん)は悲しむだけだ」と涙ながらに叱ってくれた。
「生きていかなければ」そう思い直した箱石さんは、2人の子どもと共に前を向こうと決めた。