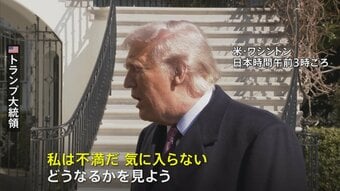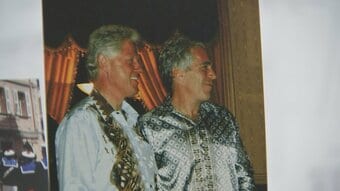各地の系列局が伝えた酷暑下の避難
特別番組の放送に伴い、特に津波警報発表区域を受け持つJNN各局は、安全を最優先に、沿岸部で住民の避難の動きに関する取材を進めた。JNNの放送内容とTBS NEWS DIGに掲載された記事などをもとに、今回の遠地津波への対応をめぐって気になったことを記したい。
東北放送(TBC)は、仙台市若林区荒浜地区にある津波避難場所「避難の丘」の様子を上空から撮影した。

東日本大震災後に造成された高台の上に、最大6400人が収容可能な広場がある。しかし直射日光を遮ることができそうな場所は、広場の片隅に屋根付きの小さなスペースが1か所あるだけだ。TBCによると、この高台に避難していた50代の女性が熱中症の症状を訴え病院に運ばれたという。当日の仙台市の最高気温は32.0℃だった。

北海道放送(HBC)も、むかわ町にある消防庁舎の屋上に付近の住民が避難している様子を伝えた。もともと津波避難場所に指定されていたということだが、こちらも日射を避けられるスペースは少なく、わずかな日陰の部分に身を寄せている避難者の姿が痛々しい。当日のむかわ町の最高気温は27.2℃だったが、日照時間は12.2時間と比較的長かった。


また岩手放送(IBC)は、久慈市内のある公民館を取材していた。館内にエアコンはなく、避難してきた付近の住民ら約110人は扇風機で暑さを凌いだという。当日の久慈市の最高気温は30.4℃だった。


災害時に避難所となる可能性がある全国の公立小中学校の体育館と武道場の空調(冷房)設備の設置状況について、文部科学省が5月1日現在の調査結果を公表している。それによると、空調(冷房)設備の設置率は全国平均で22.7%に過ぎない。
特に北海道と東北地方は、43.4%の山形県を除いて軒並み一桁台に留まっている。ちなみに地震が起きる6日前の7月24日には、北海道北見市で最高気温39.0℃を記録していた。北海道でも気温40℃が現実になりつつある今、冷房のない理由に「寒冷地だから」という言い訳はもはや通用しないだろう。