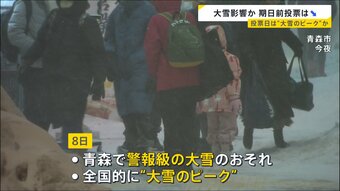SNSの偽情報に関する“注意喚起”と“ファクトチェック”に乗り出した!
SNSでの偽情報・誤情報や生成AIで簡単に制作できるようになったフェイク動画やフェイク音声などに関する注意喚起や「ファクトチェック」の報道が各局で急増した。
2016年の米大統領選挙でトランプ氏が最初の当選を果たして“フェイクニュース”が話題になって以降、ファクトチェックの必要性がメディアの中でも叫ばれていたものの、テレビ局が本格的に選挙でファクトチェックを実施したのは今回が初めてのことだ。
石破総理が「消費税20%」や「水道料金40%アップ」を明言したというYouTube動画(いずれも偽動画)など、具体的な事例を示して事実を深掘りして真偽を示した。
ネット上に散乱する膨大な偽情報について真偽を調べて「これは誤りです」と示すことは膨大なエネルギーと時間を要する。従来の報道の感覚からすればとてもハードルが高いといえるが、日テレ、NHK、TBSが突出して実践していた。
「選挙情勢」のプロセスを解説して視聴者に明らかに
「選挙情勢」や「情勢報告」といえるニュースも選挙報道にはつきものだ。これはその時々で各社が電話などを使って調査したアンケートなどを基に有権者の投票動向を調査するものだ。それぞれの選挙区や比例代表などの票数の見込みを積み上げていき、序盤、中盤、終盤などのタイミングごとに報道する。
「今月20日に投開票が行われる参議院選挙について、JNNが中盤情勢を分析した結果、自公で参議院の過半数を割り込む可能性があることがわかりました」などのニュースがこれにあたる。
こうした「情勢調査」のニュースは調査した“結果”だけをまとめて一方的に伝えるスタイルが以前は一般的だったが、今回の2025年参院選で大きく変わった。どうしてこんな予想になるのか。多くの局がその理由や予想プロセスまで解説するようになったのだ。
7月7日のフジの「イット!」を例にとると、「自民党の過半数維持は難しく、与党の過半数維持をめぐる攻防になっている」と報じた。その理由としてフジ系列のFNNが全国の「1人区」全てを対象に行った電話調査によると「自民党候補は14の選挙区で優勢あるいはやや優位」で「野党候補は11の選挙区で優勢またはややリード」していると背景を解説した。
他にも7月15日(火)の日テレ「news zero」では政治部の竹内真デスクがスタジオに登場して「1人区」の勝敗見通しなどの一覧を示した。自民党が圧勝すると考えられていた選挙区で参政党などの野党系候補が優勢になっているという。
こうした解説が加わるようになって視聴者も「なぜメディアがこの時点でこんな予測を立てたのか?」を理解できる。こうした情勢調査を丁寧に解説するようになった変化はなぜ生じたのか。
従来は、大きな選挙の選挙期間が始まると、有権者にとっては投票の基準となる「争点」について十分に報道で知る前に選挙戦の“序盤”から「〇〇党が優勢」などの“情勢”が報じられていた。
そうすると多くの人は「自分が投票する前からすでに結果がある程度は決まっているではないか⁉」と選挙への疑念を持つようになり、失望や無力感につながる。そうした情勢調査の報道のあり方も、近年投票率がどんどん下がっていく背景の一つだと考えられる。
これを転換させて「予測の理由」や「予測のプロセス」を丁寧に説明することで、一方的に結果だけを伝えていたのに比べると有権者の信頼を獲得しやすくなるのではないか。選挙への関心を促して投票への参加意欲も高まる可能性がある。そうした効果も考えた上での各社の方針転換なのだろうか。
ちなみにこうした“情勢調査”の報道について、テレビで報じているのは民放だけである。NHKは世論調査として各党ごとの支持率を発表するものの、選挙区ごとの“情勢”には触れず、選挙戦の途中の“情勢”についても報道していない。
あくまで世論の動向を伝えるというスタンスに撤して選挙の予測報道はしない・・・と公共放送として一線を画している印象を受ける。ただ、有権者の一人として見れば民放に比べると材料が乏しいため予測がしにくい面がある。自分が参加する意識を持ちにくいのも正直なところだ。