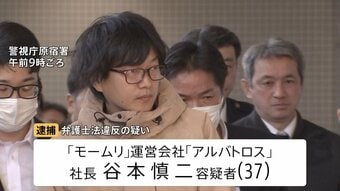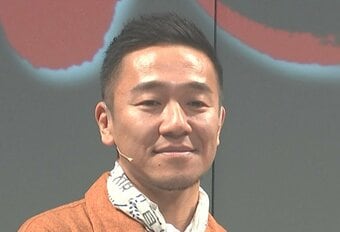高市政権との調整のハードル
もちろん、植田総裁は「予算編成中でも政策変更は可能だ」「来年の春闘の初動のモメンタムがどうなるかをもう少し情報が見たい」などと述べて、12月や1月の利上げを模索する姿勢を示しています。恐らく、間合いを見ながら高市政権との調整作業に入っていくのでしょう。市場関係者の間では、12月か1月に利上げという見方が大勢です。ただ、今の日銀の「論理建て」では、利上げへのハードルは、結構、高いのではないでしょうか。
今の「論理」は、「アメリカの関税政策の影響がどの程度かもう少し見たい」というもので、そこでフリーズしています。では、12月になれば、「その影響が無視できるようになった」と言い切ることができるのでしょうか。
また、今回公表された日銀の物価の見通しは、「いったん来年度に2%を割るレベルにまで低下して、再来年度に再び2%に上昇する」という内容です。来年度に物価が下がっていくことがわかっているのに、なぜ今利上げなのか、説得力がありません。「今利上げするのはアホや」と言われても仕方ないでしょう。まして、いったん下がった物価が、再び上昇基調を取り戻す経路は明らかではありません。
予想される高市政権からの疑問に、日銀は答えられるでしょうか。
今後の利上げの成否は、アベノミクス継承を信条とする高市政権が、異なる環境下でどこまで現実的になれるかだけでなく、日銀自身が利上げの正当性をどう説明できるかに、かかっているのです。まさに、植田日銀の正念場です。
播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)