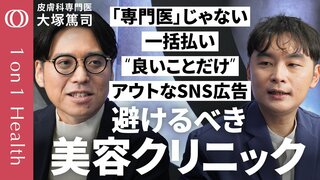制度強化の裏で進む障害者雇用の外部化 ―― 企業が抱えるジレンマと構造
日本では障害者雇用促進法にもとづき、一定規模以上の企業に対して障害者の法定雇用率が課されている。
近年、この雇用率は段階的に引き上げられ、企業の人事・労務部門にとって障害者雇用は「努力目標」ではなく、経営上の重要なコンプライアンス課題となった。
一方で、制度の要請が強まるほど、現場での受け皿づくりや業務設計が追いついていないという現実も見受けられる。
こうした中、表面的には雇用契約を結びながら、実際の就労の場が本社や主要事業所ではなく、企業の中核業務から物理的・機能的に距離のある外部の就労拠点となっているケースが広がっている。
たとえばIT企業や商社に在籍する障害者が、企業本体とは異なる環境において、当該拠点で用意された業務に従事するという構図は、一見すると柔軟な就労形態や合理的配慮の一形態とも捉えられる。
しかし同時に、それが個々の能力開発や事業戦略とどのように結びついているのか、あるいは法定雇用率の達成を主目的とした配置となっていないかについては、慎重な検証が求められる。
こうした状況は、現行の障害者雇用制度と企業行動が相互に作用する中で生じた構造的な帰結として捉えることもできる。
本稿では、この「障害者雇用ビジネス」の拡大を手がかりに、雇用を進めるための制度が、かえって実態の見えにくい雇用を生んでいるという矛盾を検証する。
その上で、企業が障害者雇用を「数合わせ」や外注化された業務として処理するのではなく、「一緒に働きたい」という関係性へと転換していくために、何が求められているのかを考察していく。
その起点は、なぜIT企業や商社の社員として雇用された障害者が、遠隔地の農園で作物を育てているのかという構造の分析にある。この光景が生まれた背景には、需給のミスマッチという構造的な問題がある。
身体障害者の採用市場はすでに飽和状態にあり、企業は今、精神障害者や知的障害者の雇用を拡大せざるを得ない状況にある。
障害者雇用の「需要側」が拡大し続けていることから、企業に対する雇用圧力が構造的に高まっている状況を裏付けている。
しかし、多くの企業現場には、障害者の特性に合わせた業務の切り出しや、精神的なサポートを行うノウハウが決定的に不足している。
「雇わなければならないが、社内に仕事も場所もない」。この人事担当者の懸念に応える形で登場したのが、就労場所と業務、そしてサポート体制をパッケージ化した障害者雇用ビジネスであった。
企業にとっては法定雇用率の達成というコンプライアンス上の課題解決であり、障害者にとっては安定した就労環境の獲得である。この「Win-Win」に見える関係性が、市場拡大の主な要因となってきた。