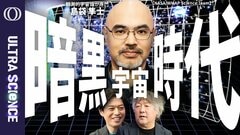製品開発時に努力の正当化が考慮されることもある
努力の正当化が注目された別の事例を見てみよう。舞台は、いまから100年くらい前のアメリカだ。アメリカの家庭ではパンケーキを焼いて食べることが一般的だ。ただ、パンケーキのもととなる粉は、小麦粉、砂糖、食塩、香料などを一定のバランスでミックスしたものを生地とする必要があり、家庭でその配合を行うのは大変だ。
そこで、製粉メーカーはそれらを適度に配合したものをインスタント・ケーキミックスとして販売するようになった。発売当初、「この製品は間違いなくヒットするだろう」とメーカーの経営者は考えた。ところが、このインスタント・ケーキミックスを買った人はすぐに使わなくなったという。メーカーはその理由を分析して、「パンケーキをつくる過程があまりにも簡単になりすぎたからだ」と結論づけた。そこで、メーカーはインスタント・ケーキミックスに粉末全卵を入れるのをやめて、パンケーキを作る際に卵を割って粉と混ぜるよう、あえてひと手間を増やした。この新たなインスタント・ケーキミックス製品は売れた。その成功の理由として、パンケーキづくりの達成感が高まり、努力の正当化が図られるようになったためとされている。
このインスタント・ケーキミックス製品に関する卵の逸話は、アメリカではよく知られている。だが、実はどうやら作り話のようだ。1950年代にこの製品の売り上げが横這いとなり、一部のメーカーが市場から撤退する事態となった。その際に、イノベーションとなったのは、卵ではなく、フロスティング(ケーキの上にかける糖衣)だったようだ。これにより、ウェディングケーキのようなケーキをつくり、デコレーションをすることが、人々をとりこにしたという。卵を割ることではなく、デコレーションをすることが、本当の努力の中身であったわけだ。
この卵の逸話は、努力の正当化が一人歩きをして、最近生成AIで問題となっている“ハルシネーション”(「幻覚」: 事実に基づかない情報を生成する現象)を起こしたものといえるだろう。