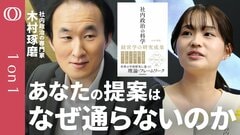「関わる」意欲と居づらさのあいだ~地域との距離感に揺れる若者
関係人口とは、地域に住むことを前提とせず、都市と地方を行き来しながら地域に何らかの形で関与し続ける人々を指す。観光のような一過的関係でもなく、移住のような全面的な生活転換でもない。
たとえば、地域イベントへの参加、オンラインでの地域プロジェクト支援、年数回の訪問滞在など、関わりの中間層を可視化する考え方である。
政策的には、地方移住を定住ではなく関わり方の選択肢として位置づけ直す点に特徴があり、2018年の第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」以降、積極的に進められてきた。
新たに発足した高市新政権も、観光・交通・デジタル・産業クラスターを地方の未来に向けた戦略軸に据え、地域と都市を往還する人の流れ、すなわち関係人口や二地域居住について言及している。
一方、現場を見渡すと、関係を持ちたいが入りにくいという声も少なくないと思われる。筆者が大学で行った地方創生のワークショップでは、ある女子学生の発言が印象に残った。
甲信越出身で現在は東京近郊の大学に通う彼女は、地方に貢献したい思いはあるが、滞在は1週間ほどが限界だという。地方は人間関係が濃く、幼少期から顔見知りが多い。
自分の過去の失敗(黒歴史とのこと)も知られていて、会うたびにその話題になることが少し息苦しい、と語った。
地方への愛着と逃避の感情が同居し、顔見知りの関係が安心ではなく時に窮屈にも感じられる。こうした原体験や心理的な濃さへの追憶が、若年層の地方との距離感を左右している部分があるようにも見える。
同様の構造は、他のケースでも確認できる。たとえば徳島県神山町を訪問した際の出来事だ。
この町はサテライトオフィス誘致やテレワーク推進の先進地として知られ、国内外から約20社が拠点を構える。
この町で働く女性の一人は、かつて町に移住していたが、現在は近隣都市から車で通っているという。
神山は魅力的な町だが、まちづくりに意欲的な移住者が増えて、穏やかな性格の自分には少しだけ合わなかったと話す。子どもの教育環境も考慮し、最終的に住居を移したが、町との関係は保ち続けたいとの想いで、通勤という形で関係を続けている。
これら二つの事例は、関係人口の核心の一端が距離の取り方にあることを示唆している。関係を深めるほど心理的な密度が高まり、距離を取りすぎると関係が希薄化して継続しない。
地方創生をめぐる関係人口の課題はこの適度な距離の設計、すなわち距離のデザインにあるともいえるだろう。