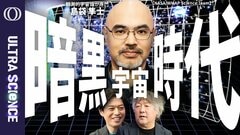日本では、街中でよく行列が見られる。スープが美味しいと評判のラーメン店、揚げ物のランチが好評の洋食店、絶品スイーツが大人気のカフェ、などなど、繁華街では人々が行列をなす店をよく見かける。
そうしたお店のグルメは、食してみると本当に美味しいことが多い。ただ、「うまい、美味しい」といった感覚は、人それぞれだ。なかには、「それほどでもなかった」と感じる人もいるかもしれない。
そんなとき、その人は後でどう考えるか。「1時間も行列に並んだ末に、ようやく食べることができたのだから本当は美味しかったに違いない。さっきは自分の感覚が少し変だったのかもしれない。そうだ、いま思い返すと料理にだし汁がほのかにきいていて、なかなか味わい深かったような気がする。やはり、長い行列に並んだ甲斐はあったようだ。」などと、行列に並んだ努力を正当化しようとする。
これは、心理学では「努力の正当化 (effort justification)」として知られている。努力の正当化は、単に自分の気持ちを正当化するだけならば特に問題はない。だが、努力の正当化にとらわれて、不合理な選択に固執したり、無意味な努力を続けたりする恐れもある。今回は、努力の正当化について、見ていこう。
努力の正当化はどのように生じるのか?
まず、用語の定義から見ていこう。努力の正当化とは、「人は、無意識のうちに、努力して達成した結果の価値を、その結果に対する客観的な価値と対比しないまま、それよりも大きいと考える傾向がある」ということを指す。
一般に、努力して達成した結果の客観的な価値が低い場合、「あんなに努力をした」という認知と、「それにもかかわらず客観的な価値が低い」という認知が同時に生まれる。
この2つの認知には矛盾が生じる。こうした2つの認知間の矛盾は、心理学的には「認知的不協和 (cognitive dissonance)」と呼ばれる。これは、アメリカの心理学者レオン・フェスティンガー氏によって提唱されたものだ。
人は、認知的不協和が生じると、ストレスを感じるようになる。そこで、それを解消して、自分に都合のよいように正当化を図ろうとする。努力の正当化は、客観的な価値との対比を無意識のうちに避けることにより、認知的不協和から生じるストレスを解消しようとするもので、そうした正当化の一つと考えられている。