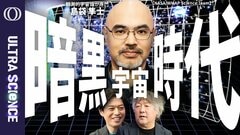努力の正当化の例
冒頭に挙げた、飲食店への行列に並んだ末に味わった料理がそれほどおいしく感じられなかったといった場合に、努力の正当化が生じることがある。その他にもいくつか例を見てみよう。
(1) 入団時の試練
何かの組織や団体に入るときに、希望者が簡単には入団できないよう、さまざまな試練を課す場合がある。代表的なものとして、企業の入社面接や、大学や高校の入学試験などが挙げられる。
その試練を乗り越えた人だけが、組織や団体に入ることを認められる。苦労して入団した人は、試練を乗り越える努力をしたことにより、たとえ以前に思っていたほどの価値が感じられなかったとしても、入団できたことに誇りや価値を見出すようになるという。愛社精神や愛校心は、こんなところから生まれるものなのかもしれない。
(2) DIY
別の例としてDIY (Do It Yourself, 専門業者でない素人が自分で修理や修繕をすること)が挙げられる。
スウェーデン発祥の大手家具量販店IKEAには、この店に由来した「イケア効果 (IKEA effect)」があるとされる。これは、ハーバードビジネススクールのマイケル・I・ノートン氏、イェール大学のダニエル・モション氏、デューク大学のダン・アリエリー氏により、2011年に発表されたものだ。
IKEAは、主として、客が自動車で持ち帰ることのできる半組立家具を開発、販売している。購入した客は、家具を自分で組み立ててから使う。その際、自分が作ったものには愛着がわき、家具の価値が高まったように感じられる。そうした心理効果が、イケア効果だ。
DIYに取り組んだ結果、出来上がったものが思っていたものと何か違うと感じられたとしよう。そんなときにイケア効果が働いて、完成したDIYの結果に何らかの価値を見出そうとする。つまり、努力の正当化が図られる。