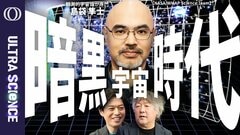ハトも努力の正当化をするか?
努力の正当化については、さまざまな実証実験が行われてきた。そのなかで注目されるのが、ハトに対する実験だ。
アメリカでは2000年に、ハトの「労働倫理」と題するペーパー(*1)が公表された。その実験はノースカロライナ州で、5~8歳のホワイトカルノーハト8羽を被験者として行われた。ハトは、まずくちばしで白色のキーをつつき、その後にあらわれる色のついた2つのキーのうち、正解のほうをつつくとエサをもらうことができる。
(*1) “"Work ethic" in pigeons : Reward value is directly related to the effort or time required to obtain the reward” Tricia S. Clement, Joann R. Feltus, Daren H. Kaiser, and Thomas R. Zentall (Psychonomic Bulletin & Review, 2000, 7(1), 100-106)
白色のキーには、1回だけつつけば色つきののキーがあらわれるものと、20回つついてようやく色つきのキーがあらわれるものがあり、ハトはどちらかを選択できた。実験の結果、20回つつくほうを選ぶケースと1回だけつつくほうを選ぶケースの比率は2:1で、20回のほうが多かったという。
この現象について、「ハトは少ない努力(1回のつつき)よりもたくさんの努力(20回のつつき)の後に生じる結果の価値を高く見ているのではないか」と解釈して、努力の正当化を図ろうとしているのかもしれないとする見方があった。
しかし、常識的にみて、ハトが人間のように“努力”を意識するとは考えにくい。この現象について、ペーパーでは、コントラスト効果(contrast effect, 無意識のうちに、2つの情報を対比することで、好ましいもののほうが、より魅力的に見えるようになる、という効果)が原因ではないかと論じている。
つまり、20回もつつかなくてはならない苦行と、その後にあらわれる色つきキーをつついてうまくいくとエサがもらえるという報酬の間のギャップは、1回つつく場合のものよりもコントラストが大きい。そのため、ハトにとって、20回つついた後に得られた報酬の魅力がより際立って見えたのではないかという指摘だ。