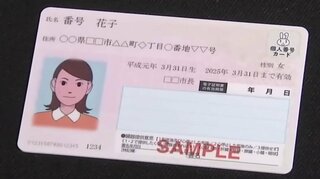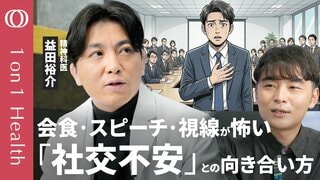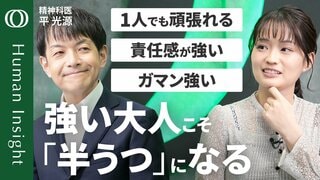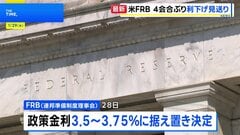夜だから「飲む」という慣習からの「解放」
一方で、現代社会においては、あえて酒を飲まないライフスタイルを選ぶソバ―キュリアス、飲みたい人は飲めばいいし、飲めない人はムリしなくてもよいというスマートドリンク(スマドリ)など、酒の消費に対する多様性が浸透しつつある。特に若者においては20年程前と比較すると20代、30代男女で飲酒習慣が低下しており、昨今言われている「若者のアルコール離れ」の様相を見て取れる。
これは、若者のナイトタイムアクティビティのスタンスにも影響を与えているようだ。SHIBUYA109 lab.が行った「Z世代のナイトタイムエコノミーに関する意識調査」では、出かける時間帯の意識について聞いているが、夜や深夜は「初対面やまだ浅い仲の相手と出かける時間」ではなく、「既に仲が良い相手と出かける時間」としての意識が強く、何か新しい出会いや仲を深めるよりも、気のおけない仲間と過ごす時間として活用していることがわかる。
また、同調査では、夜の外出におけるアルコールとの関りについても聞いているが、「まだお酒の得意不得意が分からない相手には“飲みに行こう”より“ごはん行こう”と誘うことが多い」が65.9%、「夜の時間帯のお出かけ・遊びをする場合でもお酒を飲まないことがある」が63.3%、「お酒のペースや注文、お店選びなどはお酒が飲めない人に合わせている」が59.6%と、飲酒が必須でないことや、お酒を飲まない人もいることが前提であることが伺える。1980年以降、飲みニケーションが円滑な人間関係を構築するための機会として重宝されてきたが、Z世代においては、酒そのものがコミュニケーションの“フック”になってはいないと言えるだろう。
BIGLOBEが行った「若年層の飲酒に関する意識調査」によれば特に20~24歳のZ世代においては、飲酒のスタンスに対して「特別な時のみお酒を飲みたい」が34.8%と最も高くなっている。また、飲酒へのイメージについては、それ以前の世代と比較して「盛り上がる」「特別感が出る」が高くなっている。
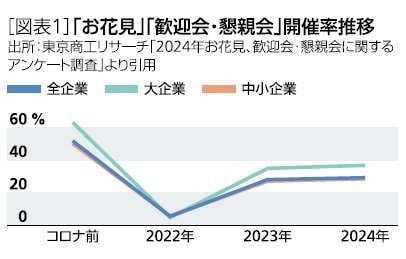
飲酒の特別感や非日常性など、消費者の飲酒に対する考え方の変化から、最近ではノンアルコール/ローアルコール専門のバーも存在している。「お酒は飲めないけれど、バーには行きたい」あるいは「お酒はあえて飲まないけれど、バーには行きたい」という消費者のために、お酒よりむしろバーという舞台性=特別感・非日常性を提供することに特化している。また、アルコールを飲む人を敢えて排除するわけではなく、アルコール入りのカクテル“も”提供している。同様に夜カフェなどでも、コーヒーや紅茶だけではなくアルコール“も”提供していることが一般的だ。前述したZ世代の調査やメインで酒が提供されるわけではないバーが市場に受け入れられていることからもわかる通り、飲酒は個々の「選択」であるべきなのだ。