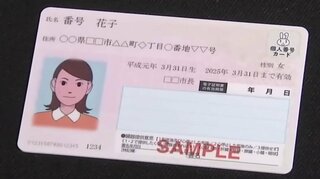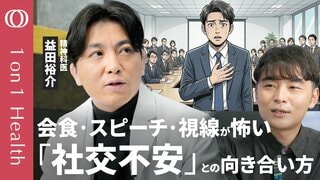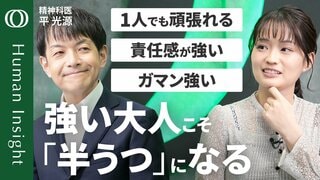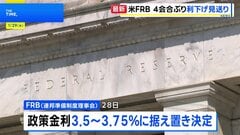飲酒も、飲酒が伴う場に行くことも「選択」の時代へ
飲酒することが強要されることなく自身で選択することができるからこそ、酒が提供されるような場所に足を運ぶというコト自体も強要ではなく「選択」対象としてのフェーズに移行しているのかもしれない。確かに上司や同僚は毎日顔を合わせる仲間であることには違いないが、同じ目的をもってたまたま集まった集団に過ぎず、自身で選んだ人間関係ではない。親密な仲間内でですら酒を飲むことが必然でないのならば、会社という組織に対するプライオリティが低下していると言われている中で、そこで生まれる上司や同僚という淡白な人間関係のために飲酒をせざるを得ないという「選択」をしなくてはいけない事自体が苦痛になるだろう。
SHIBUYA109 lab.が行った別の調査である「Z世代の仕事に関する意識調査」においては、上司を含めた会社の飲み会は好きかどうかについて「好き」が33.4%、「苦手」が66.7%となる一方で、同期や同世代の同僚との会社の飲み会が好きかについては「好き」が50.8%、「苦手」が49.1%と、上司ほどは嫌ではないが、半数近くが同期や同僚と飲む事に対して前向きではないことがわかる。
これを読んでいるZ世代の読者の中にも、同期から飲み会や仕事の後一緒に出掛けることを断られたという経験がある人もいるかもしれない。同世代だからといって、そこまで親しくない相手と仕事の後に会ったり、酒の場で話すというコト自体のハードルは下がるわけではない。同世代同士ですらそうならば、会社の飲み会や上司の誘いなら益々うれしいモノではないだろう。
個人のプライオリティが優先され、時間を無駄にしたくないと考える生活者が一定数いるからこそ、彼らとコミュニケーションをとるには、十分な配慮をする必要があり、彼らの選択を尊重してあげることが重要なのである。実際に前述した株式会社R&Gの調査では、行きたくなる飲み会の要素として「費用負担が少ない」や「短時間・一次会のみの開催」が上位に挙がっている。
「会社の飲み会で会費徴収されたけど、こっちがその分時給欲しいくらいだ」といった投稿がSNSで散見される。奢ってやるから相手はうれしいはず、という認識を捨て、相手はこの飲み会のためにプライベートの時間を割いている、別に会社での人間関係に親密性を求めていない、と認識することで、飲みニケーションの形も変化していくだろう。併せて、全ての若者がお酒を飲まないわけではなく、飲酒を好む若者がいることや会社での飲み会が好きな若者もいることも留意したい。本レポートの内容はあくまでも傾向であり、自身や自身の身の回りにいる若者には当てはまらない事もあるだろう。ただ、相手の人となりがわかるまで 飲酒の場に誘ったり、酒を勧めるといった事を配慮することも、飲酒に対する多様性が追求される現代社会において大事なコミュニケーション手法なのかもしれない。皆が皆自分と同じように酒や飲み会が好きという訳ではない、と念頭に置くことでより良い人間関係(煙たがられない)構築につながるのではないかと思う次第だ。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬涼)