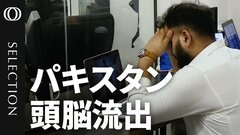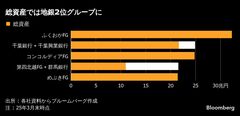(ブルームバーグ):信用を築くのは難しく、失うのはたやすい。特に国際関係においては、一度失えば取り戻すのに莫大な代償を伴う。だからこそ、米国のトランプ大統領が2期目就任から8カ月で、同国がかろうじて保っていた外交・安全保障面での信用を使い果たしてしまったことは、小さな問題ではない。
最新の失態は先週の国連演説で起きた。トランプ氏は多くの挑発的な発言を繰り返し、各国首脳は時に衝撃を受け、時に困惑し、最も深刻なことには、無関心か、または半ばあきれ顔を見せる事態となった。まとまりを欠いた演説は、国連だけでなくブラジルから英国まで各国を次々と攻撃した。
その後、トランプ氏はロシアによるウクライナ侵攻をめぐり、自らの立場をまたもや場当たり的に翻した。ウクライナは「全土を元の形で戦って勝ち取れる」とし、ロシアは「張子の虎」に見えると述べたのだ。この1カ月前、トランプ氏はロシアのプーチン大統領を赤じゅうたんで迎えていた。
それより前には、トランプ氏はプーチン氏に停戦交渉入りを迫る最後通牒を突きつけ、変更し、最後はうやむやに取り下げた。またさらに前には、ウクライナ自身に侵攻の責任があると非難したり、「ウクライナは交渉カードを一切持っていない」として領土割譲を迫ったりもした。そして常に、「もし自分が2022年にホワイトハウスにいたなら、プーチン氏は侵攻しなかっただろう」と繰り返し主張してきた。
米国大統領には国内外に多くの聴衆がいる。国際的な聴衆には、敵対国、同盟国、どちらにも転び得る国々が含まれる。ウクライナを巡る文脈での主要な敵対者は、もちろんプーチン氏だ。旧ソ連の国家保安委員会(KGB)で訓練を受けたプーチン氏の頭の中では、トランプ氏はとうに「有用な愚か者」に分類済みなのだろう。
トランプ氏が今年1月に就任して以来、プーチン氏はウクライナへの爆撃を抑制するどころか激化させ、欧州の北大西洋条約機構(NATO)諸国への「グレーゾーン」工作すら強めてきた。そして、米国から目立った報復を受けることもない。ここ数日だけでも、ロシアはドローン(無人機)をポーランドやルーマニアに、戦闘機をエストニアに送り込み、さらに北欧にもドローンを飛ばしたとされる。
トランプ氏は1期目でも米国の信用を傷つけた。北朝鮮の独裁者を威嚇したかと思えば「恋に落ちた」と言い、金正恩朝鮮労働党総書記が核計画を進めるのを傍観した。さらにアフガニスタンでは、イスラム主義組織タリバンとの間で米軍撤退について誤った合意を結び、後継のバイデン前大統領が実行に移して悲惨な撤退劇となった。
この10年間、欧州の友好国から中国のような敵対国にまで、米国の信用を疑う理由はすでにあった。トランプが2期目でやっているのは、その疑念を払拭するのではなく、むしろ信用喪失を確定させることだ。今や同盟国は米国は信頼できないと学び、敵対国は結束して、悪事やもっと危険な行動の計画を練り直している。
冷戦時代、信用は東西対立を核戦争に至らせないための戦略やゲーム理論の根幹を成した。ノーベル経済学賞受賞者のトーマス・シェリング氏は「メンツは、戦うに値する数少ないものの一つだ」と指摘した。信用、つまり核攻撃に対する壊滅的な報復の確実性こそが抑止の本質であり、それは今も変わらない。
冷戦後、核の脅威が弱まったかに見えた時代には、学者の間で懐疑的な見方が広がった。信用は過去の行動に根ざすのか、それとも米国大統領が将来取る行動に対する主観的な予測に依存するのか。認知バイアスはその認識をどう歪めるのか。コロンビア大学国際・公共政策大学院のケレン・ヤルヒミロ学部長は、多くの政策立案者が「評判のために戦う価値はない」と結論づけたと指摘する。とりわけイラクやアフガニスタンでの失敗の後に、その傾向が強まった。
2025年の今、こうした風潮はもはや時代遅れに見える。米国の信用失墜が、地政学上のライバルやならず者国家にさらなる侵攻を促しているからだ。トランプ氏が「狂人理論」によって売り込もうとした強さは、もはや気まぐれ、優柔不断、混乱による弱さにしか見えない。ヤルヒミロ氏とヒラリー・クリントン氏は、プーチン氏のような人物との個人的な相性が、戦略や専門知識、そして何より本物の決意に取って代わり得ると、トランプ氏が誤解しているとの見方を示した。
危険の兆候は至る所にある。米国のパートナーは不安を募らせ、安全保障の代替策を模索し始めている。カタールがイスラエルの攻撃を受け、米国から支援を得られなかった。それを見た隣国サウジアラビアは、パキスタンと防衛協定を結んだ。中国の習近平国家主席や北朝鮮の金正恩氏のように、好戦的なシナリオを密かに練り直す人々もいる。その他インドのような国々は、米国への全面的なコミットを避け、ロシアや中国とも手を握れるよう選択肢を残している。
米国の信用喪失に対するこのような対応は、世界的な紛争リスクを高める。もし米国が今後、現政権下でも将来の政権下でも、評判回復を急ぐあまりに過剰な対応に走り、示威的な強硬路線に転じるなら、その危険はさらに増すだろう。
(アンドレアス・クルス氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、米国の外交と安全保障、地政学を担当しています。以前はハンデルスブラット・グローバルの編集長を務め、エコノミスト誌に執筆していた経歴もあります。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Trump Has Lost Credibility Worldwide: Andreas Kluth(抜粋)
コラムニストへの問い合わせ先:Washington Andreas Kluth akluth1@bloomberg.netエディターへの問い合わせ先:James Gibney jgibney5@bloomberg.net翻訳者への問い合わせ先:London 畠山朋子 thatakeyama2@bloomberg.netもっと読むにはこちら bloomberg.co.jp
©2025 Bloomberg L.P.