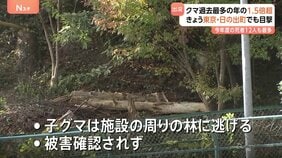小沼地区でほうきづくりが始まったのは、明治のころ。
深い雪に閉ざされる冬の副業として広まり、最盛期の昭和20年代から30年代は100人ほどが、ひと冬に3万本以上生産していました。

鈴木芳美さん:
「ほうき小屋でみんな集まって。5、6人ずつね、ほうき小屋で座って。真ん中にストーブやまきを燃やして、上で肉でも煮て。終わると同時に(お酒を)やる。みんな楽しみで」
小沼地区の女性:
「私がやり始めたときに教わった方も高齢になったり、亡くなっちゃった方もいたりして、あと数年で終わっちゃうなという感じはありましたね」
掃除機や洋間中心の住宅の普及で、ほうきの生産量が減るとともに生産者もわずか数軒にまで減少。
危機感を持った地元の有志は2018年、振興会の前身にあたる「小沼ぼうきを守る会」を結成して生産と販売を始め、翌年、県の伝統的工芸品に指定されました。
現在の会員は12人。
講習会を開いて普及活動をしたり、地区内の畑でほうきの材料となるホウキグサ(ホウキモロコシ)を栽培・収穫しています。