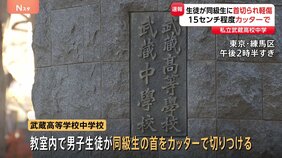がん患者の温存・生殖医療は保険の適用外となっています。大分県は治療費を補助する制度を国に先駆け、3年前の2020年に導入。これまで22人に対して合わせて280万円を助成しました。
(県健康づくり支援課・長峯友美さん)
「県下の病院・医療従事者の方が患者さんに助成制度を伝えていただくことで、少しずつ広がってきていると思います」
2人目の出産控え…「温存を選択して良かった」
長男を出産した時にはなかった制度を活用して、木下佑美さんは夫婦で再び生殖医療を受けました。来年3月には2人目の男の子の出産を控えています。長男は弟の誕生を待ちきれない様子です。

(5歳の長男)「弟と一緒にラジコンで競争したい。あと自転車の乗り方を教えて、一緒に乗って遊びたい」
当初は考えていなかった子どものいる暮らし。佑美さんは「まさか自分が病気になって、妊孕性温存治療をすることになるとは思わなかった」と話し、迷いながらも温存を選択して良かったと振り返ります。
(木下佑美さん)
「やっぱり病気になったことに意識がいってしまい、保存の話をもらわないとそこまで頭が回らなかった。当たり前に誰もが知ってるようになれば、お子さんを授かれるっていう機会が増えるんじゃないかなと思います。産まれたら自分でもびっくりするぐらい意識が変わるんで、チャンスがあるのであれば、してたほうがいいのかなとは自分の経験から思います」
生殖医療を巡っては経済的負担などまだ課題はあります。ただ多様な生き方を尊重する今の社会で、がん患者にとってひとつの希望になっているのは確かです。