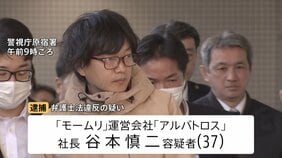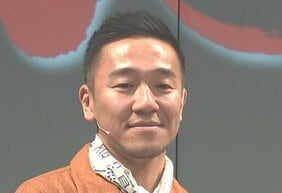2024年、設備の故障に伴って、水深が深い、近くの中学校のプールで行われた、高知市の長浜小学校の水泳の授業で、4年生だった男子児童が溺れて死亡した事故で、事故原因などを検証していた検証委員会が、最終的な報告書をまとめました。報告書は300ページを超えていて、主な事故原因に、「児童の場所の把握、教諭の役割分担」をあげています。
この事故は、2024年7月、設備の故障に伴って近くの中学校で行われた、高知市の長浜小学校の水泳の授業で、4年生だった男子児童が溺れて、死亡した事故です。
2024年8月以降、水難事故や医師、体育授業などの専門家を委員とする検証委員会が8回にわたって、事故の経緯や事実関係について調査し、きょう、最終的な報告書が公表されました。
報告書では、それぞれの専門家が分野ごとに事故原因などを分析していて、内容は300ページを超えています。
例えば体育の授業の視点では「設備故障による授業の代替を急ぐあまり、教諭間の協議がなされないまま、校長判断で中学校のプール使用が決まったこと」や、水難事故の視点では「男子児童の身長対してプールの水深が深かったこと」などが原因として考えられるとしています。
そのうえで直接的な原因を「教諭の一人が、なくなった男子児童の居場所を把握しないまま授業を進めたこと」そして、関係する主な原因を「別の教諭が泳ぎが苦手な子の活動に参加しなかったこと」と結論付けました。
さらに、学校、教育委員会に関しても、「深さへの対策を講じていなかった」と指摘しています。
また、再発防止策として各学校の施設や環境などを鑑み、「ゆとりのある時間軸で授業進行ができる内容を検討すること」や授業の実施者と監視者の役割を分けること、さらに、泳ぐ技能の獲得を急がず、溺れないための技能を確実に習得させることなどを提言しました。
最後には「委員会がいかに事実を検証し、原因を分析したうえで、児童の失われた命や希望にあふれた未来は永遠に戻ってくることはなく、残された遺族の悲しみが癒えることは決してない。本件事故は取り返しのつかない事故で、本来、水に慣れ親しみ、溺れないための技能を習得すべき授業中に起こった事故である点で、決してあってはならない。学校、教育委員会の関係者にあっては、取り返しのつかないものであることを深く胸に刻み、再発防止策を確認するのみならず、原因、背景、事実経過を十分に吟味し、独自の視点で、児童らの命を守るための再発防止策を構築し、徹底していただきたい」としています。
検証委員会は午後から最終報告書について会見を行う予定です。