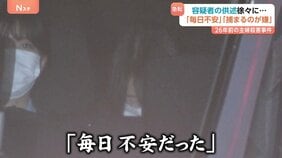野々村チェアマンが描く“30年後のJリーグ”は
なかなか想像するのが難しいじゃないですか。
ただ、僕の勝手なイメージですけど、30年前って、今イングランドのプレミアリーグが世界で一番。これはたぶんそうなんだと思うんですね。
30年前って、別にそんなに変わらなかったんですよ。Jリーグとイングランド・プレミアリーグって、売上とかも含めて。でも、こんなに差がついている。逆に言うと、やりようによっては、30年でそのくらいの差は埋まるし、もしかしたら差がつくし、ということなんだと思うんですよね。
で、30年後にヨーロッパ(のサッカー)が今のままでいるとも限らない。アメリカはアメリカで、ちょっと違ったビジネスモデルでサッカーのリーグを始めて、うまくいくかもしれない。
そうなると、ヨーロッパをビジネス的に目指すよりも、JリーグはJリーグとして、日本のサッカーとして、アジアの中の中心としてどうなっていくのがいいのかみたいなことを考える方がちょっと面白いのかな思っていて。

たぶん30年後にはたぶんサッカーの世界のバランス、パワーバランスもきっと変わっている中で、やっぱりJリーグはJリーグとしての魅力をしっかりと出すことができるようになっていれば、世界の中でもアメリカ・ヨーロッパ・日本みたいなことになっていてもおかしくない。
どこかの“まねごと”をするよりも、自分たちは何が強みで、どうなっていくのがいいのかみたいなことを考えるのが良いのかなと。
Jリーグが“勝負”できるポイントは
―Jリーグでどこが勝負できるかなと思うと、ピンと来ないのですが…野々村チェアマンが思う、ここで勝負できるんじゃないかなというポイントは?
今、例えばヨーロッパがトップだとして、そこに人が流れていく、選手として流れていくっていうのが、現在。数年前から今はそうですよね。その流れに逆らう必要はないと思うので、日本という国から、日本の中心選手がヨーロッパに出ていくのは今までもあります。
ここからたぶん、もっと周りの国で言うと、東南アジアとかアジアって、サッカーがまだまだ日本よりは少し劣るけど、サッカー人気が爆発的に伸びそうな国がいっぱいあるんですね。そこの選手たちがJリーグで活躍できるようになり、かつ、じゃあヨーロッパに出ていくみたいなことが、10年後ぐらいにそういう風になっていくなら…
例えば、チャナティップというタイの選手(タイ代表・現 J1川崎フロンターレ所属)を札幌が獲った時、「Jリーガーになりたい」と思っていた子どもは日本の子だけだと思っていたら、タイの子どもたちもJリーグに行ってみたいと思うようになっていった。それが例えば東南アジアの子どもたちがみんな思い始めたら、それはそれでJリーグの価値が上がります。

それでJリーグがアジアの中で圧倒的な存在感を示していきながら、ビジネスでもうまく成功していくと、だんだんとヨーロッパとのビジネス的な差は埋まっていくと思うんですよね。そのときに、日本はどれだけ安全かということが、他の国からすると信じられないほど安全で安心なわけですよ。なので、サッカーだけではなくて、国の魅力として、あの国に行って住みたいなと思う海外の選手はたくさん出てくるし、今もいると思うんですよ。そのビジネス的な、給料が少し上がるくらいの“ビジネス的な成功”があれば、日本という国の魅力で多くの人が来ると思っています。
(聞き手:大塩綾子BSNアナウンサー 撮影日:3月10日)
◇野々村芳和 Jリーグチェアマン
1972年、静岡県清水市(現 静岡市清水区)生まれ。愛称は“ののさん”。
強豪の清水東高校から慶応義塾大学に進み、卒業後はJリーグのジェフ市原でプロキャリアをスタート。2000年に札幌に移籍すると、J2優勝に貢献。
2001年にけがの影響もあり現役引退し、その後はサッカー解説者やコメンテーターとして人気に。2013年には札幌の運営会社“コンサドーレ”の社長となり、クラブ経営に携わる。その後2022年に、“第6代 Jリーグチェアマン”に就任。Jリーガー出身のチェアマンは史上初。