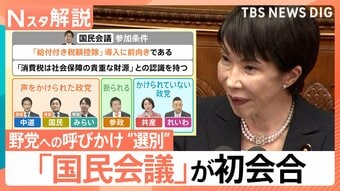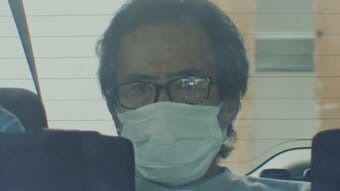ーーえ、ボーン上田賞受賞した方が、カメラも苦手ということですか?
カメラの正面で話すのが嫌で、今でもカメラマンにどう撮りますか?と聞かれると「とりあえず後ろからついてきて」ってお願いしています。
ーーでも、ネット配信番組を見ていると、カメラの存在を気にせず、自由にしゃべり続けているイメージです。
支局のスタッフにも「1分の原稿は間違えるのに、90分のリポートよく間違えないですね」なんてよく不思議がられます。たぶん原稿にしても、カメラ目線にしても、予定調和なことが、嫌というより、できないんだと思います。ネット配信のときのように、原稿がないリポートだと、カメラを気にせず、いくらでも話し続けられるんですよね。

■「現地の人にとにかく寄り添おう」ガザ地区で変わった伝え方
ーーボーン・上田賞の受賞理由に「迫力ある映像、生の声はテレビの強みである。その強さを須賀川記者が実証して見せている」とありました。その場で起きたことをそのまま伝える須賀川記者だからこそなんですね。昔から「民衆の声を伝えたい」という思いが強かったのですか?
もともとそういう気持ちは強かったです。なぜなのか、理由はよくわからないんですが、よく思い出すのは中学の時の友達のことです。
私は子どものころの大半を海外で過ごしました。中学生の頃はオーストラリアに住んでいたのですが、インドネシア人の友人がたくさんいました。ですが、インドネシアで通貨危機があって、急にほとんどの友達が帰国をしなくてはならなくなりました。お別れのパーティーで悲痛な表情だった友人や家族のことをよく思い出すんです。
昨日まで当たり前だった生活が、自分ではどうにもできない理由で大きく変えられてしまうことがあると知りました。そして、徐々にですが、私にできることがあるなら、そんな自分の責任ではないことに生活を翻弄されている人々のために時間を費やしたいと考えるようになりました。

ーー記者になってそれはすぐ実践できたのでしょうか?
事件や事故、災害の被害者に寄り添いたいという気持ちで記者になったものの、何をどのようにしたらいいのか、はっきりとはわからないままでした。でも、中東支局長になって大きな転換がありました。
赴任したてのころは、中東で起きていることをどう伝えたら日本で関心を持ってもらえるのかと悩みました。最初は日本にどうつなげるか考え、中東で活動しているNGOの日本人を取り上げるなどしました。でも、出来上がったものを見て、どうもうまくいってないと感じました。
なぜかと考えたときに気づいたんです。頭の中で“主役が日本”だったんですよね。でも違うよなって、初めてガザ地区に取材に行ったときに思いました。日本人に伝えるために切り口を考えるのではなくて、現地で起きていることをそのまま伝えないと意味がないって。
ガザ地区で起きていることはあまりにも凄惨で、起きていることをそのままちゃんと伝えなくてはいけないと思いました。