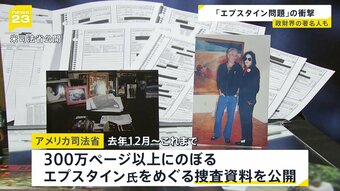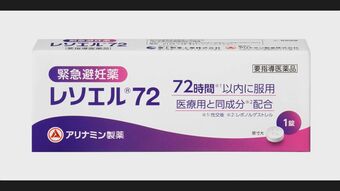SNS選挙のプラス効果は投票率の向上、しかし多くの重要な問題点も
ネット空間で、利用者に対しての働きかけを積極的に行い、支持を拡大した国民民主党・参政党が政治参加を促し、投票率は58.51%と、2022年の52.05%を約6.5%上回った。時事通信社の出口調査(比例投票先)では、無党派層の14.5%が国民民主党に投票し、自民党(14.1%)、立憲民主党(13.6%)を上回り、参政党も13.3%で既成政党と肩を並べた。
ネット空間の活性化が、これまで政治に関心を持っていなかった層の政治への関心を呼び起こし、投票率の向上に結び付いたことは、これからの政治参加のプラスの側面として肯定的に捉えていいだろう。
しかし、既存のマスメディアが、先述したように、選挙期間中に抑制的な報道をしている中で、ネット空間が活性化することに課題も生じている。
第一は、分かりやすさの陥穽だ。以前からも、分かりやすいキャッチフレーズで争点を単純化する手法は、「郵政民営化」「政権選択」など、ポピュリズムの手法で有権者を動かしてはきたが、こういった分かりやすさは、一方でそれ以外の重要な政治課題を見えにくくし、有権者の認知を歪めかねない。今回の参院選でそれが典型的に表れたのは「外国人問題」だろう。
NHKが、「参院選」「選挙」というワードとともに、Xに投稿されている内容を、6月中旬から7月中旬にかけて1か月分調べた結果を報道しているが、投稿件数は「少子化」が約4万1000件、「安全保障」が11万3000件、「関税」が11万8000件、「コメ関連」が14万2000件、「年金」が14万6000件、「物価高」が18万8000件、「消費税」が67万4000件、そして最も多かったのは「外国人」で、119万件で、7月10日以降急増している。
マスメディアのニュースでも、外国人による問題は、事件事故で取り上げられることにより、実態とは異なるイメージが増幅されていた部分がある。政治はエビデンスに基づく施策が求められるが、急に外国人問題が取り上げられた背景には、政党の議題設定がネット空間で増殖し、マスメディアや他の政党も取り上げる相乗作用が生まれたことがある。「分かりやすさ」には、そこに含まれる多様な側面が捨象される危険もつきものだ。
第二は、真偽不明の情報の拡散だ。マスメディアは真実性を何より重要視するが、ネット空間は違う。アテンションエコノミーはじめ、注目を集めるためなら、虚偽情報をも厭わない、というのは憂慮すべき状況だ。
公職選挙法では、第235条第2項で「当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」こととされているが、実際の適用は、表現の自由との兼ね合いで難しく、これまで抑制的だった。
しかし、選挙期間中にネット空間が虚偽の情報で歪められる現実に対して、たとえば共同通信社が2025年5月に行った郵送方式の世論調査では、選挙の際、真偽不明の情報がSNSで拡散することに「法律での規制が必要」を選んだ人は58%、「事業者などの自主的な規制が必要」が29%に上った。表現の自由とのせめぎあいの中での規制を世論は求めている。
政党や既存のマスメディアも「ファクトチェック」を行っているが、政党によるファクトチェックは自党の主張の正当化に用いられることも多く、マスメディアや中立の専門機関がファクトチェック機能を強化することがより求められよう。
第三は、SNSは国境を越えて影響する点だ。昨年11月のルーマニア大統領選挙では、勝つ見込みのない「泡沫候補」として扱われた極右候補がSNSを通じて支持を急拡大させ、得票率で首位に躍り出て不正が指摘されて選挙は無効となったが、外国勢力の関与が指摘された。
今回の参院選でも、選挙期間を前にロシアによる大規模な情報工作が日本のSNS空間で激化していることが指摘され、7月16日の記者会見で、青木一彦官房副長官が、SNSを使った外国勢力の介入の可能性について問われ、「我が国も影響工作の対象になっているとの認識のもと、国家安全保障戦略で対応能力を強化することとしており、外国からの偽情報の収集・分析や偽情報への対外発信について一体的に推進している」と述べ、関係機関が連携して対応に当たっていると説明した。
今後、外国勢力の関与をチェックし、情報操作により民意が歪まないように警戒することがますます重要になろう。
今回の選挙で「SNSとポピュリズム」がより鮮明になったとはいえ、有権者に伝達する手段としてSNSが定着し、そこに、シルバー民主主義のもとで政治有効性感覚に乏しく、政治参加が十分でなかった層が政治参加し始めた、という構図で見れば、SNSを活用して多様な民意を掬い取る民主主義の新しい形が模索されているともいえる。
だからこそ、SNS時代の大衆民主主義においては、有権者のリテラシーが何より重要だ。
イギリスの政治学者グレアム・ウォーラス(Graham Wallas)は、選挙権が拡大し、大衆民主主義が広がっていく中で、『政治における人間性』(1924年)を著し、
「投票を通じて表現される『意見』自体を信頼に足るものにしなければ、『意見』をいくら広く募ったり正しく反映させたりしても意味がない」
「大概の人間の政治的意見は大部分、経験によって検証された理性的推理の結果ではなくて、習慣によって固定された無意識の、あるいは半ば意識的な推論の結果」
であると、ポピュリズムに流されやすい民主主義の脆弱性を喝破し、リテラシー教育こそが枢要であると説いた。メディア環境が変化したとしても、正確な情報を提供し、正確な情報をもとに判断する民主主義を常に目指すことが、民主主義の劣化を防ぐ。
今回の参院選は、過去の歴史的教訓を、あらためて思い起こさせる選挙だったのではないだろうか。
<執筆者略歴>
川上 和久(かわかみ・かずひさ)
麗澤大学教授。専門は政治心理学、広告と社会心理、戦略コミュニケーション論。
1957年生まれ。東京大学文学部社会心理学科卒、東京大学大学院社会学研究科社会心理学専攻修士課程修了、同博士課程単位取得退学。
1986年東海大学文学部専任講師。1991年同助教授、1992年明治学院大学法学部助教授、1997年~2016年同教授、2003~2008年法学部長、2008~2012年副学長。2016年~2020年国際医療福祉大学教授。2020年より麗澤大学教授。
1997年『メディアの進化と権力』(NTT出版)で大川出版賞受賞。
著書に、「18歳選挙権ガイドブック」(講談社・2016)、「昭和天皇玉音放送」(あさ書房・2015)、「反日プロパガンダの読み解き方」(PHP研究所・2013)「イラク戦争と情報操作」(宝島社・2004)、「北朝鮮報道:情報操作を見抜く」(光文社・2004)、「情報操作のトリック:その歴史と方法」(講談社・1994)など。
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版のWebマガジン(TBSメディア総研発行)。テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。原則、毎週土曜日午前中に2本程度の記事を公開・配信している。