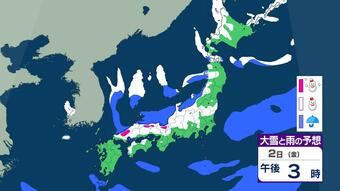駅やイベントなどで女性用トイレに長い行列ができる問題について、国土交通省が改善に向けた有識者会議を開催しました。
政府は6月に決定した骨太の方針で、女性用トイレについて「利用環境の改善に向けて対策を推進する」としていました。
これを受けきょう、国土交通省で有識者会議が開かれ、事業者からトイレの設置数の考え方などについて発表がありました。
有識者会議では今後、▼駅やデパートで行列の改善対策を行っている事例を共有するほか、▼便器の数の男女比の基準などを見直して、ガイドラインとしてとりまとめる方針です。
なぜ女性用のトイレに行列ができるのか。専門家はスマートフォンの普及や、洋式トイレの広がりなどを指摘します。
日本トイレ協会 小林純子 名誉会長
「トイレがゆっくりする場所になっていますし、それ自体は悪いことじゃないと思っていますけれども、スマホをされてちょっとゆっくりしたり、和式から洋式化になると椅子みたいなゆっくり感がありますので、多少の占有時間の拡大はあると思います」
そのうえで、行列問題解決に向けて国が動き出したことに期待感を示しました。
日本トイレ協会 小林純子 名誉会長
「国が姿勢を見せてくださったということは、本当に嬉しいことだなと思ってます。私の力だけではどうしようもないっていうところを少しずつ崩していくっていう皆さんの機運が出てくるっていうのが、すごくいいことかなと思ってます。みんなが意識するという大きな波になることは事実だと思います。それが私一番大事だと思ってます。10年後にまた同じように『女性ばっかり待っているのよ』っていうような、発言が出てこないような世界になるといいと思います。それこそが、今よく言われてる男女平等に繋がっていくのではないかなと思います」
ただ、国土交通省が事業者を対象に行った調査では、▼建物の構造によってはトイレのスペースを広げるのが難しいこと、▼資材費の高騰で、改修費用や維持管理の費用が増えてしまうことが課題としてあげられています。
注目の記事
「明治のラストサムライ」305人 東北に残した足跡…囚人として、武士として生きた薩摩の男たち

お尻から血や膿が出続けるクローン病 10代~20代中心に10万人近い患者、多感な時期に社会と距離… 「一人で悩まず、当事者のつながりを」

「出せなくてごめん」妻子が倒壊ビルの下敷きになった居酒屋店主 遠く離れた神奈川から“復興の力”に 能登半島地震2年

1月1日生まれは「誕生日ケーキが食べられない?」 元日営業を30年続けるケーキ店「求められる限り続けたい」

【言葉を失ったアナウンサー】脳梗塞による失語症 「話すのは、アー、ウーだけ」…最重度の “全失語” を乗り越えたリハビリの日々【第1話】

「やっと技術が認められた」従業員約70人の町工場が開発 量産可能な最高水準の緩み止め性能のボルト 【苦節21年の道のり 開発編】