控訴理由は事実誤認だったが… 高裁判決は量刑を検討「“人生を破壊”はいささか過剰な評価」

男側は、1審判決には「事実誤認」があるとして控訴。
大阪高裁(坪井祐子裁判長・安永武央裁判官・荒木未佳裁判官)は2024年12月の判決で、事実誤認の主張は退けた。
しかし高裁判決は「職権で」量刑について検討した。
高裁判決は、同様の性犯罪事案の量刑の幅について、上限がおおむね懲役14年から15年に分布しているとした上で、1審判決は「この上限を突出して超えていて、虐待の末の傷害致死の量刑をも凌駕している」と指摘。
娘の被害結果についても「性犯罪の中に重大な精神的被害が伴うものが少なくないことは、従来から承認されている」「1審判決は、人生を破壊する結果をもたらしたとみても過言ではないなどと説示しているが、いささか過剰な評価といわざるを得ない」とした。
「程度が類例を見ないとも言いがたい」「従来の量刑傾向から著しく乖離」2審は刑を5年減らした
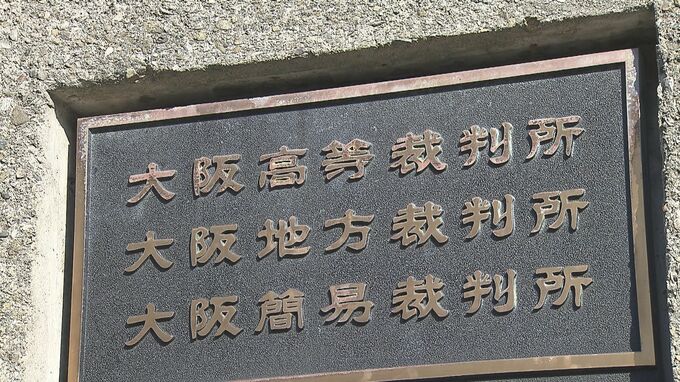
さらに悪質性・常習性の面についても「1審判決の評価に誤りはないが、この種の事案で卑劣な態様による犯行が常習的に繰り返された後に発覚する例が散見されることからすれば、程度が類例を見ないとも言いがたい」と判断した。
そして「1審で裁判員を含む裁判体が、被告の責任が非常に重いと判断したのは尊重されるべきで、同種事案の量刑の幅の上限程度=懲役15年程度に処することまでは許容できるが、これを大幅に超えることは、従来の量刑傾向からの合理的理由のない著しい乖離であり、重すぎて不当」と結論づけ、1審判決を破棄し、男に懲役15年を言い渡した。
男側はこの判決も不服として上告したが、最高裁が上告棄却決定を出し、今年6月14日付けで男の懲役15年判決は確定した。
物議を醸した判決… カギとなった判例

裁判員裁判制度は、市民の視点や感覚を反映させるという目的で導入された。裁判員を含む裁判体が下した量刑から、職権で5年も刑を減らした高裁判決は、大きな議論を呼んだ。
刑事裁判に詳しい近畿大学法学部の辻本典央教授は、MBSの取材に対し「2審の大阪高裁は、2014年の最高裁の判例に従ったと考えられる」と指摘する。














