「“この事件だけ量刑が突出するのは妥当ではない”という評価。やむを得ない判断では」
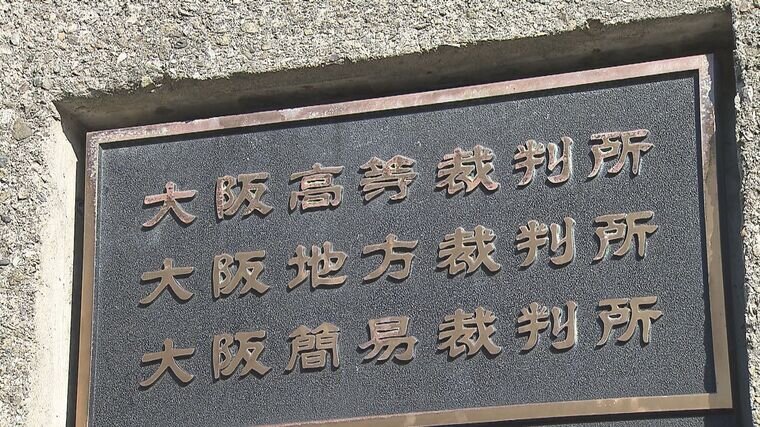
今回の、娘に対する実父による性的暴行事件では、仮に複数の起訴がされていれば、刑法が定める「併合罪」の原理が適用され、有期懲役刑の上限が30年となっていた可能性がある。
1審の大阪地裁判決も、実質的に保育所の頃からの性加害を認定した形ではあったが、起訴された事実は、あくまで2022年の性的暴行“1事案”のみだった。なので、刑は20年までとならざるをえない。
そのうえで辻本教授は「2審の大阪高裁としては、“1審が懲役20年の量刑が妥当と判断した様々な事情も、精査すると同種の事件が複数あった。したがって、この事件だけ量刑が突出してしまうのは妥当ではない”という評価だった。やむを得ない判断だったのではないか」と分析した。
「緩やかに量的傾向が変わっていく可能性もある。今回の1審判決が否定されるべきではない」
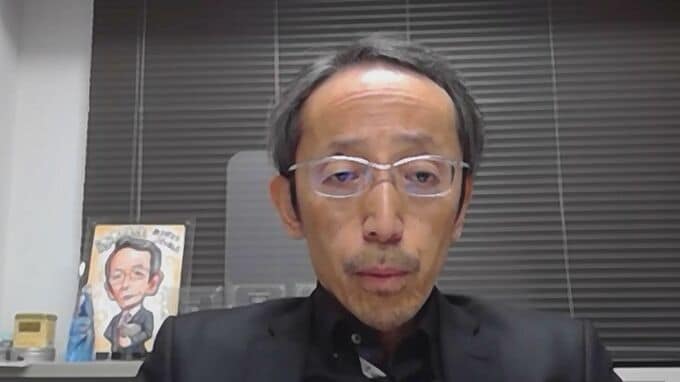
一方で、辻本教授は次のようにも語った。
「高裁では覆ったが、裁判員裁判が20年の判決を下したこと自体は、ひとつの事例として良かったと思う。今後こうしてひとつずつの事例が積み重なっていけば、緩やかに量的傾向が変わっていく可能性もあるし、今回の1審判決が否定されるべきではない」














