離島移住の研究者「コミュニティが地球の負荷を減らす」

大会では夜に交流会も行われ、滋賀県や大阪府の自治体関係者や地域リーダーらも出席。2日目は分科会が開かれ、現場で環境問題に取り組む団体や個人の話に、若手の公務員などが次々に意見し、実践の知恵を共有しました。
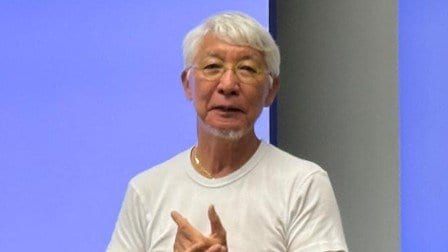
石田秀輝さん(東北大学名誉教授/地球村研究室代表)
登壇者の一人で、鹿児島県・沖永良部島(おきのえらぶじま)に移住した研究者石田秀輝さん(72)はこう語ります。
「地球に環境負荷をかけない暮らしとはどんな暮らしか。移住を通して学んだのは、自然との親和性、“人と人とが支え合う”コミュニティが幸福度も増して文化度が高いということでした。いかに私たちの利便性を求めた人間活動の肥大が自然に負担をかけているか、もっと知り、行動すべきです」
「エコロジカル・フットプリント」という考え方では、
元・環境事務次官の中井徳太郎さん(公益財団法人三千年の未来会議代表)はこの大会の主催者の一人。官僚時代の経験から、この経済社会を一刻も早くリデザインすることが重要で、地球を、世界を変えるには、日本人の世界観がとても重要だと指摘します。
「地球沸騰とまで言われるこの時代。脱炭素社会、循環経済、分散型自然共生社会の3つのサステナビリティの実現には、自然資本を充実させ、良好な環境をつくり、生活の質を高めることが「新たな成長」を生み出すということを知ってほしい。そういう意味では今こそ地球に必要なのは、古来から自然の循環の中で生きてきた日本人の世界観、つまり『シン・ジャポニズム』そのものなのです」
















