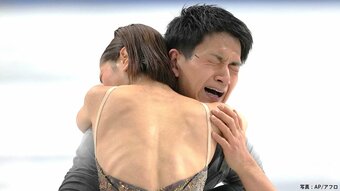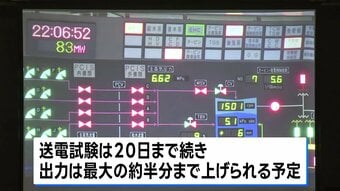衆院選と兵庫県知事選を受けて2025年の課題
特に兵庫県の出直し知事選で議会の全会一致で失職に追い込まれた斎藤元彦知事が再選されたことは、テレビで司会者を務める宮根誠司に「テレビなど既存メディアは敗北した」と言わせ、安住紳一郎アナもショックを隠しきれないという表情になり、TBSの井上貴博アナは「テレビの選挙報道のあり方を考え直していく」と宣言した。
だが、今後、どのように選挙報道を変えていくのかという具体的な対策はテレビ画面ではほとんど語られてはいない。2025年には参議院選挙が予定されているが、さらにSNS戦略が選挙結果に影響を与えることは確実だろう。筆者は今のままのテレビの選挙報道では有権者の期待に応えることがますます出来なくなっていくのでは?という強い危機感を抱いている。
兵庫県知事選の後で、NHKの日曜討論が「いま考える選挙とSNS」という討論番組を放送した(11月24日)。国際大学准教授の山口真一氏やAIエンジニアで起業家の安野貴博氏が「2024年が転換点になった」という意見で一致していた。
今回のエム・データによる集計で、選挙期間中に衆議院選挙に関連した放送時間は、【図表1】から44時間あまりだということがわかる。NHKと民放5局合わせた放送時間で44時間あまり。
ところがSNSに目を転じてみると、YouTubeで様々な討論番組をやっている元テレビ東京の高橋弘樹氏が運営しているReHacQが選挙期間中に東京の選挙区を中心に候補者座談会の生配信を行っている。人気バラエティ番組を制作していた高橋氏だけあって、全体的に進行の裏側もそのまま見せるという「楽しい」作り方になっている。
筆者が調べてみたところReHacQでは東京の30選挙区のうち21選挙区で生配信というかたちで候補者討論会を実施。おおむね1時間から2時間の長さになっていた。それぞれの再生回数が20万回などになっている。21選挙区で1時間の番組としてもそれだけで21時間だ。選挙期間中の地上波テレビの選挙報道の総計の半分近い時間になっている。
実際に視聴者がどちらを深く視聴するのかはこの数字だけではわからないが、兵庫県知事選では多くの有権者がテレビとSNSを対照的な存在としてコメントしていたことが思い出される。
「テレビはぴたっと報道しなくなったけど、(YouTubeなど) SNSで探せばもっと詳しい情報がたくさんあった」
「テレビは何か嘘があるのか本当のことを言わないけれどSNSは本当のことを言ってくれる」
そう感じて斎藤元彦氏に投票した有権者は少なくない。
ReHacQだけではない。PIVOTやNewsPicks、選挙ドットコムちゃんねるなど、SNS経由ではそれぞれ独立したメディアたちが活動している。それらを総計すれば、テレビの放送時間などをはるかに超えるくらいの動画などのコンテンツがSNSには存在している。
ReHacQなどの動画を探して視聴していたら、その流れで「選挙まであと3日 石丸伸二氏が語る政治」というタイトルの動画を見つけた。面白い。あの石丸氏に話させるのか・・・と思ってみたら、それは石丸氏がよく登場するReHacQではなく、毎日放送のYouTubeチャンネルだった。関西ローカルの番組で放送した特集映像をYouTubeで視聴できるようにしていた。ただ、残念なことにわずか5分あまり。滋賀県でのトライアスロンに出場した石丸氏にインタビューをして3日後に投開票が迫った衆院選について感想を聞いている。
「よくある国政選挙になって非常に残念な気もしている」と石丸氏。
ReHacQならば1時間以上のトークにできるはずだ。せっかくの石丸氏の登場なのにもったいない。今のテレビ局の選挙報道のコンテンツはどうしても地上波の放送尺で映像をつくってそれを配信するので、物足りないものになってしまう。それゆえ魅力が乏しいのだ。
今後、来年の参議院議員選挙などでテレビ局もネットでの「報道」をもっと充実させるためには、ReHacQなどのように長い尺で「見やすい」配信コンテンツを出していく必要がある。現状でテレビ局が国政選挙などの際に有権者に向けて出すとしたら、本来ならば信頼性が高いテレビ局が本気でReHacQのような選挙コンテンツを参考にして、より長尺で魅力的な選挙コンテンツ作りに取り組んでいくしかないのではないか。
2024年はSNSが選挙に大きな影響を与えたエポックメーキングな年だった。
では2025年はどうなるのだろう? これまでのような横並び意識が強いまま大胆に工夫しなければ、ますます有権者からは見限られてしまうのだろう。2025年はテレビの選挙報道にとってその真価が問われる年になることは間違いない。
<執筆者略歴>
水島 宏明(みずしま・ひろあき)
1957年生。東京大学法学部卒。
札幌テレビ、日本テレビで報道記者、ロンドン・ベルリン特派員やドキュメンタリーの制作に携わる。生活保護や派遣労働、准看護師、化学物質過敏症、原子力発電の問題などで番組制作をしてきた。
「ネットカフェ難民」という造語が「新語・流行語大賞」のトップ10に。またドキュメンタリー「ネットカフェ難民」で芸術選奨・文部科学大臣賞を受ける。
2012年より法政大学社会学部教授、2016年より現職
【調査情報デジタル】
1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。