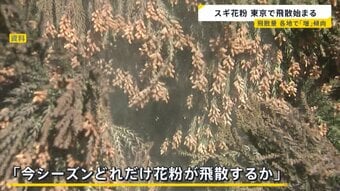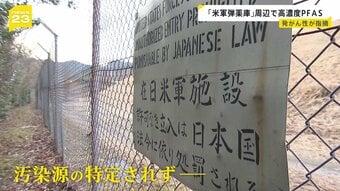テレビの選挙報道は視聴者の期待に応えられていないのではないか?テレビはSNSに「負けて」いるのではないか。ジャーナリストで上智大学文学部新聞学科教授の水島宏明氏が緻密なデータ検証に基づき論考する。
2024年は選挙が変わった年だった!
「2024年は日本の選挙のありようを大きく変える年になった——」
4月の衆院選補欠選挙、7月の都知事選、10月の衆議院議員選挙、さらに兵庫県議会での全会一致の不信任決議を受けての知事失職にともなって実施された11月の出直し知事選挙。そこで有権者が示したのは新聞やテレビなど「既存メディア」への強い不信。そしてSNSへの依存と信頼だった。政治にかかわる多くの関係者や識者や研究者やメディアの関係者が少なからず衝撃を受け、選挙でのSNSの影響力の大きさを認めざるをえなかった。
とりわけ兵庫県知事選では、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑とおねだり疑惑。それを内部告発した元幹部職員に対する“犯人探し”の是非をめぐってテレビや新聞で連日大々的に報道していたにも関わらず、選挙の時期が近づくと公職選挙法や(特にテレビやラジオの放送局は)放送法を意識して、「公平」「中立」を意識するあまり、ニュースなどの報道は型どおりのパターンになってしまう。
なぜ斎藤氏が失職することになったのか。その背景について以前ほど報じられなくなって、各候補をほぼ均一に扱うお決まりの機械的な報道になってしまった。各候補を横並びで扱うことになってしまった。
それが有権者にとっては、候補者について一番情報を知りたい選挙期間中に情報が「届かない状態」になった。テレビなどの主要メディアは本当に重大な情報を有権者に対して隠している。そんな疑惑の声がSNS上で広がった。
マスコミは“真実”を意図的に隠している。それを伝えているのはSNSだという陰謀論が広がり、「既存メディア不信」とむしろ「SNSを信頼する」という声が選挙のたびに大きくなって投票行動にも影響を与えた。
なかでも選挙の公示(あるいは告示)の後から投票前日までの「選挙期間中」はテレビなどのメディアが上記のお決まりの定型的な報道ばかりやって、しかも時間を十分にとらない。各候補を一律に紹介しようとする。そのことで有権者がほしい情報が届かない「空白」が生じた。
それが既存メディアも想定していなかった“石丸現象”や“斎藤知事返り咲き”などにつながったと見る識者は朝日新聞にこうした談話を発表した日本大学危機管理学部の西田亮介教授など少なくはない。
実際に時間の制約が少ないSNSと連動する配信コンテンツの方が候補者らの主張をたっぷりと見ることができて、SNS(YouTubeなどの動画メディアも含む)の方が信頼できると評価し、そちらを利用して投票を決めたという人が増えているのが現状だろう。
SNSは時にフェイク情報や個人への誹謗中傷を含む場合があるとしても新聞やテレビよりも柔軟に、楽しく、見やすいスタイルで大量に情報発信している。本当にテレビはSNSに負けてしまったのだろうか。
本原稿では2024年の衆議院議員選挙について首都圏で放送された地上波テレビの選挙報道についてふり返りながら、テレビの選挙報道には何が足りないのか。現状がどうなっているのかを検証していきたい。
参照したのは地上波テレビの番組やCMの放送内容と放送時間などをデータ化している株式会社エム・データから提供を受けた「TVメタデータ」である。同社から提供されたデータを筆者なりにアレンジし直して分析したのが以下の論考である。