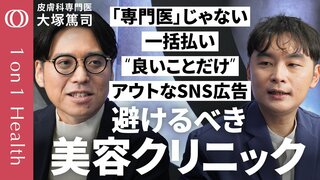「加害者」も追いつめられている現実
虐待の背景を探る第一の視点は、「加害者」とされる人々もまた、支援を必要とするほどに追いつめられているという現実である。
高齢者虐待の発生要因として最も多いのは「被虐待者の認知症の症状」(56.4%)であり、次いで「介護疲れ・介護ストレス」(54.8%)が挙げられる(厚生労働省「令和5年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果」)。
しかし、これは認知症の人が悪いということではない。症状への対応の難しさと、適切なケア方法を知らないことによる行き詰まりが、虐待の誘発することを意味する。
障害児・者の介護においても、出口の見えない24時間体制のケア、睡眠不足、経済的負担、社会からの孤立が、養護者である家族の心身を極限まで疲弊させる。
彼らは「助けて」という声を上げることさえできず、あるいはどこに助けを求めてよいか分からないまま、一人で重圧を抱え込んでいる。
施設における虐待も本質は同じである。現場における慢性的な人手不足、低賃金といった労働環境、そして専門性の高いケアに対する教育体制の不備は、職員を「バーンアウト(燃え尽き症候群)」させ、感情のコントロールを失わせる要因となり得る。
もちろん、いかなる理由があっても虐待は正当化できない。しかし、データが示すのは、虐待を誘発する要因が純粋な「悪意」であるケースだけでなく、過剰な「疲弊」と「孤立」が限界を超えた結果として、不適切な対応がエスカレートしていくケースが多いという事実である。
虐待に至った家族や職員は、加害者であると同時に、本来であれば利用できるはずの休息サービス、相談窓口、労働環境の保護といった公的支援にアクセスできず、社会的に孤立無援の状態に置かれ、支援を必要としていた「当事者」でもあったといえる。
「閉鎖性」が助長する虐待の温床
虐待の背景を探る第二の視点は、虐待が発生しやすい環境、すなわち「閉鎖性」の問題である。虐待は「家庭」と「施設」という、外部の目が行き届きにくい「密室」で発生し、深刻化する。
かつての日本社会には、良くも悪くも地域コミュニティのつながりがあり、「お節介」とも言える近隣の目が、育児や介護の困難さを分散させ、同時に監視する機能を果たしていた。
しかし、都市化と核家族化、そして近年のコロナ禍が地域社会の関係性を希薄化させ、多くの家庭が「孤立した育児」「孤立した介護」を強いられている。
「家庭内の問題」として外部から見えにくくなった結果、問題は水面下で深刻化し、SOSが発せられた時にはすでに手遅れ、という事態を招きやすい。
福祉施設もまた、本質的に「閉鎖空間」となりやすい構造を持つ。入所施設では、利用者の生活の場と職員の職場が一体化し、外部の多様な価値観や視線が入り込みにくい。人手不足の中で日々の業務に追われる職員間では、コミュニケーションが不足しがちになる。
こうした閉鎖的な組織風土の中では、一人の職員による不適切なケアが他の職員に伝播しやすく、次第に感覚が麻痺していくという「負の連鎖」が起こり得る。
また、問題を認識した職員がいても、「組織の和を乱したくない」「告発しても握り潰される」という同調圧力から、内部告発が機能しにくいという問題も指摘されている。
虐待防止の鍵は、この「閉鎖性」を打破し、「透明性」と「風通し」を確保することである。
家庭や施設を「開かれた場所」にし、地域包括支援センターや相談支援専門員といった専門機関、あるいはボランティアや近隣住民といった「外部の目」と積極的につながることが抑止力となる。