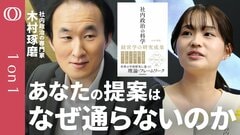保育の受け皿(量)の拡大から、保育の質を重視した政策に
こども家庭庁は、2024年12月20日に「保育政策の新たな方向性」を公表した。
待機児童対策を中心とした「保育の量の拡大」政策は一定の成果をあげたとして、2025年度から2028年度末を見据えた保育政策では「量から質への転換」を推進するとしている。
「量から質への転換」を行うために設定されたのが、「地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実」「全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進」「保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善」の3つの柱である。
以下、公表された資料をもとに、それぞれの柱の内容と背景について確認する。
(1) 1つ目の柱:地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
1つ目の柱では、(一元的な対策ではなく)地域の現状や課題に合わせた保育提供体制を整えることの重要性が提示された。
併せて、保育の質の確保・向上の取組みを進めるとしている。
背景に、待機児童の大幅な減少により、個別のニーズに関心と資源を集中できるようになってきた状況と、人口減少の問題がある。
こども家庭庁「保育政策の新たな方向性(参考資料)」によれば、待機児童は2024年4月1日時点で2,567人まで減少した。
依然として都市部を中心に待機児童が生じているものの、過疎地域などでは保育所等の定員充足率が低下してきており、保育提供体制の地域別での計画的な整備が必要となっている。
また、保育の量の拡大により待機児童が大幅に改善された一方で、保育現場での事故や不適切な対応事案なども発生している。
安心・安全な質の高い保育提供体制の強化が必要となっており、具体的な施策に職員配置基準(子どもの年齢や人数に応じて最低限必要とされる保育士の数)の改善などが掲げられた。
これにより保育士1人当たりの担当するこどもの数が減り、よりきめ細やかな保育が可能となる。
(2) 2つ目の柱:全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進
2つ目の柱では、「(家庭外での)保育の必要性のある家庭」への対応だけでなく、全てのこどもの育ちを支えるための取組みや、家族支援、地域の子育て支援の強化が掲げられた。
具体的な施策として、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で保育所等を柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」(2025年4月より制度化、2026年4月より本格実施予定)などが創設された。
(3) 3つ目の柱:保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善
3つ目の柱では、業務の効率化と保育の質の確保・向上を図るために、保育人材の確保の一層の促進と、テクノロジーの活用等による業務改善の推進が掲げられた。
こども家庭庁「保育政策の新たな方向性(参考資料)」では、その背景として、保育士の有効求人倍率は2024年4月時点で2.42倍と全職種平均(1.18倍)と比べて高い水準となっていること、後述する配置基準の改善や「こども誰でも通園制度」の制度化により保育士が引き続き必要となる見込みなどが挙げられている。
保育の質向上の最重要課題は保育人材の確保
「量から質への転換」を支える3つの柱の内容と背景について概観したが、質の高い保育の提供や全てのこども・家庭への支援は、保育士が確保されている前提で可能になる。
そのような意味で、3つ目の柱「保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善」(とりわけ保育人材の確保)が最重要課題といえる。
そこで、保育士不足が叫ばれる現状と背景について整理したうえで、保育人材確保へ向けた今後の対策のあり方について考察する。