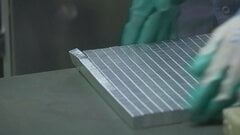岩手県では経営側委員全員が退席
この決定に衝撃を受けたのが、お隣の岩手県です。岩手県は昨年は1円差で下から2番目、一昨年は全国最下位と、秋田県と競う間柄です。秋田県の決定から3日後、岩手県の審議会は79円引き上げて、秋田県と同じ1031円とすることを決めたのです。
どの県も「最低賃金の最低県」にはなりたくないものですが、岩手では、経営側委員5人全員が「強い反対」の意思を示すとして、退席する中で採決が行われました。その他の県でも、経営側委員が退席する例は発生しており、労働側、経営側、公益委員の3者が「十分話し合って決める」という、これまでの慣行が変質してきたことを表しています。
結局、国の目安を上回る引き上げを決めたのは、39道府県に及びました。今年度、秋田県に変わって最下位になったのは、沖縄、宮崎、高知の3県の1023円ですが、この3県も引き上げ幅は71円と、目安の64円に比べれば大幅です。これで、すべての県で最低賃金は1000円台を達成しました。全国加重平均も、当初の目安をさらに3円上回る1121円となりました。
昨年の徳島県84円引き上げが契機に
今回、各県によるいわば上積み競争の契機となったのは、昨年、徳島県が84円という破格の引き上げに踏み切ったことでした。徳島県の後藤田知事は、県独自の試算を行って「現行の最低賃金は、生産性など徳島県の経済実態からかけ離れている」と大幅引き上げの旗振り役を務めたのです。
徳島の場合は、大阪や神戸と橋と道路で繋がっていることから、最低賃金の大きな格差が人材流出につながっているという危機感も大きかったようです。これまでは、国の目安にせいぜい数円上積みするのがやっとだった各県が、一気に四国トップに躍り出た、昨年の徳島の「成功」に、大いに刺激されることになったのです。