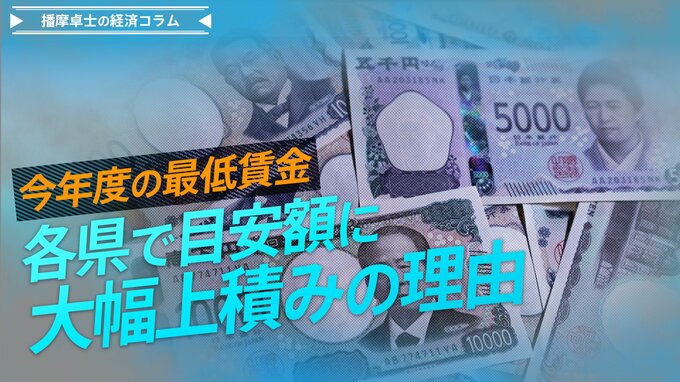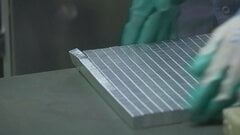都道府県ごとに決まる、今年度の最低賃金が出揃いました。各地で国の目安額を大きく上回る決定が相次ぎました。来年の春闘に向け、賃上げのモメンタムが続くと期待する声がある一方、地方経済への逆効果を懸念する声も上がっています。
国の審議会は過去最大の引き上げ提示
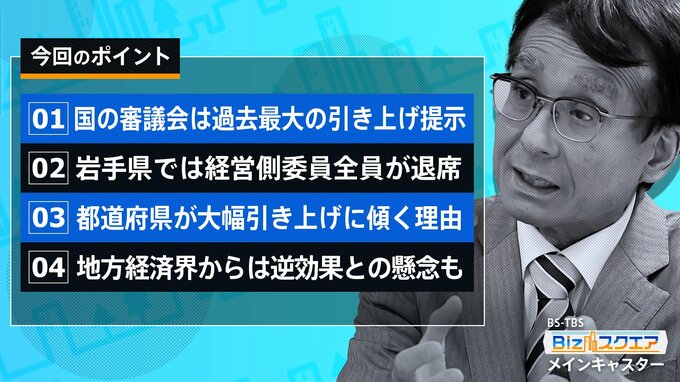
最低賃金は毎年夏に国の審議会が引き上げ額の目安を決め、それを受けて、各都道府県がそれぞれの最低賃金を決める仕組みになっています。今年は、8月4日に厚生労働省の審議会が25年度の最低賃金の目安を、全国の加重平均で63円、率にして6%引き上げて、時給1118円とすることを提示しました。目安の引き上げ幅は過去最大で、食料品を中心とした物価高や、「2020年代に時給1500円」という政府の目標にも配慮したものでした。
その上で審議会は、経済実態によって3つに分けられた全国各県について、賃金の低い秋田や沖縄などCランクの13県は64円、賃金の高いAランクの6都府県と、残りのBランク28道府県については、63円を引き上げ幅の目安としました。
最下位脱出に向け、秋田県80円上げ
これを受けて行われた各県での審議では、目安を大きく上回る決定が相次ぎました。最大の引き上げ幅となったのは熊本県で、目安の64円に18円も上積みし、82円の引き上げを決めました。次いで隣の大分県が81円の引き上げで決着。人手不足感が強まる中で、さながら近隣県との「最低賃金引き上げ競争」の様相を呈しました。
中でも、これまで時給951円と全国最下位だった秋田県は、8月下旬に早々と、16円上積みした80円もの引き上げを決め、各県に衝撃を与えました。なんとしても単独最下位からの脱出を、という秋田県の鈴木知事の要請も、異例の高い引き上げ決定の後押しになりました。
もっともあまりの引き上げ幅に、公的な事業者支援の準備が必要だとして、引き上げ実施を、通常の10月から、来年3月31日に先延ばしする異例の措置が取られました。