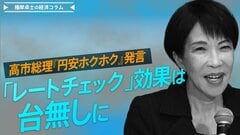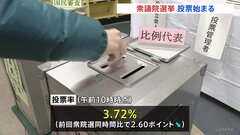Z世代とサステナビリティにおける「ジレンマ」の背景にあるもの
1|世間の目とSNS、そして「間接互恵性」~利他をためらう見えない圧力とインセンティブの不足
さらに複雑なのは、日本社会特有の「世間」と言われる外部環境・秩序の存在である。
ある先行研究によれば、日本社会には特有の「世間」という秩序があり、人々は「社会に評価されるか」よりも「周囲(世間)にどう見られるか」を基準に行動を調整してきた、と言われる。
しかし、サステナビリティは海外から「外来」概念として導入され、まだこの「世間」の枠に十分組み込まれていないため、「善いことをすれば評判が返ってくる」という間接互恵性、つまり「直接的なお返しはなくても、周囲からの信頼や評価として見返りが得られるという仕組み」が働きにくい、と言われる。
結果としてZ世代にとっては、「利他的に見える行為」が逆に評判を損なうリスクと映りやすく、「意識高い系」と見られることの回避が優先されてしまう傾向もあると言えるのではないだろうか。
さらに、SNSによる行動の可視化がそれを助長している面もありそうだ。実際にはサステナ行動を評価する人は多いものの、「やりすぎると浮いてしまう」という誤解が重なりブレーキがかかることもあると思われる。
先行研究によれば、人は実際の規範(社会が評価すること)と、自らの思い込み(「みんながそう思っているはずだ」という信念)を混同しやすいとされる。
Z世代はSNSによって常に可視化されている世代であるがゆえに、「利他的に振る舞えば意識高い系と見られるはず」という誤解を強めやすいとも考えられる。
そうだとすれば、「ピュアな利他性」を前面に打ち出す訴求は、逆に、Z世代から見ると押し付けがましい印象を与え、響きにくい可能性があるだろう。
さらに、「やりすぎた親切(利他)」を嫌う空気から、特に、周囲(世間)の目を気にするZ世代にとっては行動抑制の要因となり得る。