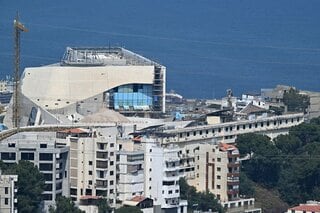要旨
▼2025年の死亡者数は約162万人と予測されている。また、2050年頃まで毎年約160万人が亡くなる見込みだ。日本は「多死時代」を迎えているといえそうだ。
▼2023年の死亡者約160万人の死亡場所内訳をみると、病院死(約104万人)が最も多い。一方、在宅死(約27万人)や施設死(約25万人)も決して少なくない。死亡場所の割合の経年変化をみると、2010年頃から病院死が減少し、施設死と在宅死は増加している。
▼死亡場所の構成比の変化には「社会環境」「国民意識」という大きく2つの要因が作用している。本稿では社会環境変化の観点について考察する。施設死の割合が高まる理由を社会環境変化の観点から検討すると、高齢者向け施設の数が増加し、施設看取りを支える体制が整備されてきたことなどが挙げられそうだ。
▼在宅死割合の増加理由を社会環境変化の観点から検討するにあたって見落とせない視点に「孤独死」の問題があるだろう。「孤独死」と「在宅看取り死」のどちらが在宅死の増加に影響しているのかを分析したところ、「在宅看取り死」の影響が大きく、在宅看取りが広がりをみせていると示唆された。
▼在宅看取りが増える理由には、在宅看取り体制が充実し、在宅医療と在宅介護の連携が進んできたことなどが挙げられそうだ。一方、表裏である病院死割合が減少する理由には、医療機関機能が高齢者向け施設・自宅へ分散化してきていることなどが指摘できる。
▼続稿では死亡場所の構成比の変化に「社会環境」とともに作用する「国民意識」にも焦点をあてる。まず施設死・在宅死への国民期待の程度を確認し、「最期の居場所」の割合が今後どのように変化していくのか、その展望を考察する。そして「多死時代」に高齢者向け施設や自宅で最期を迎えるうえで重要性が高まる「看取り介護」に必要な視点などについて私見を加えたい。