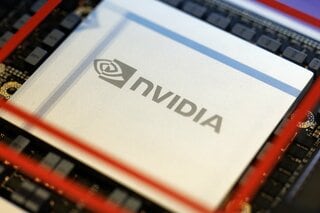「わざわざ」自分が消費する意味を考える
コーラの中にチューイングキャンディのメントス数粒を一度に投入すると、泡が一気に吹き上がる現象を「メントスガイザー現象」という。
聞いたことがある方もいらっしゃると思うが、実際にこれを行った人はそんなにいないと思う。それは「わざわざ」やるまでもなく、結果を知っているからだ。
新型コロナウイルスが流行して世界中でステイホームが強いられた際、家でできる娯楽として様々なSNSでこのメントスコーラが投稿され、メントスコーラがタイムラインやリコメンドに溢れている時期があった。
多くの有名YouTuberも同じような投稿をしており、コーラにメントスを入れると噴き出るという事実は、周知なモノとして認識されていったが、これは結果を見ることによって疑似体験をしていたと言えるだろう。
我々は、この例のように日常生活において他人の消費結果を参照したとき、わざわざ自分が体験する必要があるのか、購入する必要があるのかを無意識下で見定め、消費を行っているのだ。
他人の消費結果を参照し、「わざわざ」自分が消費する必要があるか検討する上で、消費者は(1)価値、(2)動機、(3)比較、(4)効用の高次化、(5)正しく消費、の5つの要素を検討していると考えられる。
まず、(1)価値とは、ここまでの説明でも触れたように、どのような消費結果が待ち受けているかを認識したうえで、わざわざ自分がお金や時間を消費してまでも経験すべきかという必要性を検討することである。
(2)動機とは、シンプルに消費欲求を充足したいと思うことであって、消費結果を知ったからこそ喚起されたものである。
(3)比較とは、手間や費用を要する消費を検討する際の費用対効果や、その消費を行わなかったことで行える消費の検討である。限られた予算の中で「Aはやってみたいけど、Bはわざわざ自分がやるほどのことでもないな」「AをやるとBができなくなるがそれでいいのだろうか」、と消費のプライオリティを天秤にかけることであり、極めて日常的なことである。
(4)効用の高次化とは、実際に消費する際は、他人の消費結果を参照した上で、もしくは情報を収集した上で消費を行うことでよりお得に、より効果的に消費、しようとするモチベーションである。
(5)正しく消費とは、他人の消費の失敗を顧みて間違いのないように消費をすることである。身長170㎝でMサイズのズボンを買ったら丈が短かった、というレビューがあったとしたら、170cmの自分がわざわざ同じ商品を買うのにMサイズを選択して失敗する必要はないだろう。
他人の消費を踏まえて消費をすることは正しい(間違いのない)消費をする上での指標となるのと同時に、積極的に消費をしない理由を検討することにも繋がっているのである。
タイパが良いか悪いかは「主観」
時間の短縮化という意味では、時間を極力かけないタイパ志向の方が合理的であると思われるが、Z世代にとってはどれだけ時間がかかったとしても情報を収集する事で、消費に失敗するリスクを下げる事が効率的であると評価する層がいることを本稿を通じて確認した。
時間が短ければ短いほどいいと思われるタイパだが、時間(タイム)のパフォーマンス(成果)という側面からタイパを見るのならば、消費に失敗する事はタイパが悪いことであり、調べる事にかかる時間そのものは時間の無駄ではなく、無駄なことに消費をしてしまった場合の購買経験=時間を無駄として評価していると言えるだろう。
消費に失敗したくない、間違った消費をしたくないという意識から、入念に情報を取得し、慎重に消費を行う事は、その無駄な時間を省くことに繋がり、結果的にタイパの向上につながっているのであり、あくまでもタイパに対する評価は主観なのである。
実際にSHIBUYA109 lab.が行った「Z世代の時間の使い方に関する意識調査」の時間を効率的に使うためにやっていることという項目を見てみると、21.3%が、「失敗しないように念入りに情報収集した上で買い物」と回答している。
このようないわば「脱タイパ」志向は、限られた元手(お金・時間・機会)の中でQ.O.C(= Quality of Consumption)を向上させる事が目的となっているのである。
しかし、これは当然と言えば当然の話なのだ。そこまで重要度が高くなく、処理するだけで済む情報ならばそこまで時間はかけないし、それこそ家や車などを購入する際は調べすぎるに越したことはない。
タイパ時代だからと必ずしも何でもかんでも時間の効率化が求められている訳でなく、自分にとってプライオリティが高ければ自然に多くの時間をかけている。ただ、Z世代にとっては、そのようなプライオリティの高さを生み出す要因が、他世代に比べ極めて強い「消費に失敗したくない」という意識なのである。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼)