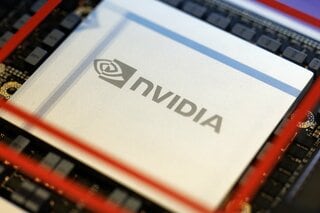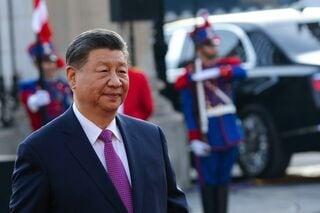4――男性育休取得推進の課題
4-1│性・世代別にみた家事育児分担に関する意識
3までに、女性活躍を進めるために、男女役割分業の見直しが必要であること、その方法として、企業が男性育休取得を推進していくことが重要であることを説明してきた。ここからは、国内の男性の育休取得の現状と課題について整理する。
これまで、男女役割分業意識が日本社会には根付いてきたと強調してきたが、実は若年層に限れば、意識は変わり始めている。
図表5は、夫婦間で家事育児をどのように分担したいかについて、内閣府の「令和4年版男女共同参画白書」をもとに、性・世代別に調査結果をまとめたものである。その結果、男性は「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど夫婦で「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増え、「外部サービスを利用、それ以外は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)の割合が減っていた。
例えば育児について数字を確認すると、「半分ずつ分担」または「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」を希望する「50~59歳男性」は60.3%だが、「18~29歳男性」では74.4%に上り、10ポイント以上上昇した。逆に、「育児は配偶者が多く分担」(妻が多く負担すること)を希望するのは、「50~59歳男性」では19.6%であるが、「18~29歳男性」では9.4%と、半分以下となった。
女性の意識も概ね、「家事」と「育児」のいずれに関しても、若いほど「半分ずつ分担」「外部サービスを利用、それ以外は半分ずつ分担」という希望割合が増える傾向が見られた。
4-2│若年男性の育児休業取得への希望
4-1でみた若年男性の育児に対する積極的な意識は、育児休業への希望にも表れている。
2024年6月に厚生労働省の委託事業「イクメンプロジェクト」が18~25歳の男女を対象に行った意識調査では、男性の育休取得に関する希望は「取得したい」が39.4%、「どちらかというと取得したい」が44.9%で、合わせて84.9%が取得を希望していた(図表6)。
希望する育休取得期間は、最多は「1~3半年カ月未満」の25.3%だったが、半年以上を希望する回答も、合わせて約3割に上った(図表7)。
4-3│若年男性の育児休業取得の現状
若年男性の家事育児への意識が変化し、育休希望も強いのに対し、職場の状況はどうだろうか。
厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」から最新の男性の育児休業取得率をみると、2023年は30.1%となり、10年連続増加した(図表8)。前年度に比べると13.0ポイントの大幅な増加である。
昨年度、急増した背景には、育児・介護休業法改正により、2022年10月から、出産や妊娠を報告したすべての従業員に、育休取得の意向確認や法制度の説明が企業に義務付けられたことや、2023年度から、従業員1,000人以上の大企業を対象に、男性の育休取得状況の公表が義務付けられたことなどが挙げられる。
また、男性育休の取得期間を見ると、2023年度は「3~6か月未満」が28%と最大の構成割合となっている(図表9)。2018年度には、「5日未満」と「5日~2週間未満」で合わせて7割を超していたことを思えば、質的にも大きく前進したと言える。
ただし、育休取得率を企業規模別にみると、従業員30人以上の企業は32.2%だったのに対し、5~29人の企業では26.2%など、小規模な企業ほど割合が低かった。また4-2で紹介したように、取得を希望する男性は8割を超えていることや、希望取得期間は約3割が半年以上としている状況と照らすと、実際の取得状況は、十分ではないと言える。
4-4│男性の育児休業取得の課題と今後の見通し
それではなぜ、若年男性は希望通りに育休を取得できていないのだろうか。
日本能率協会総合研究所が2023年、小学4年生未満の子がいる男性の正社員・職員に対し、末子の誕生後、育休を取得しなかった理由を尋ねたもの(複数回答)が図表10である。
これを見ると、トップは「収入を減らしたくなかったから」という金銭面の理由だが、2位以下を見ると、「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから」(22.5%)、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」(22.0%)、「残業が多い等、業務が繁忙であったから」(21.9%)など、職場の意識や職務の属人化、働き方に関するものが2割を超えて多かった。「昇給や昇格など、今後のキャリア形成に悪影響がありそうだと思ったから」(9.6%)という、いわゆる「育休ペナルティ」を挙げた回答も約1割あった。
従って、今後の課題としては、企業トップが男性育休取得に向けて号令をかけて、社員の意識改革を促すこと、休みを取っても業務が停滞しないように、仕事の属人化を止めて、予め組織や部署で仕事の情報をシェアしておくこと、休業期間の長さ等によっては臨時社員を雇うこと、育休を取得したことがその後のキャリア形成でマイナスとならないような評価制度を運用すること――などが必要だと言える。
さらに、社内で育休取得経験がある男性社員の実例を共有すること、つまり男性の両立に関するロールモデルを示していけば、次第に、上司に「育休を取得したい」と言いやすい職場の雰囲気に変わっていくだろう。
4-1でみたように、管理職に多い50代では男性の育児に対する意識が異なるため、特に上司側に注意が必要である。因みに、育休を取得した男性への金銭面のサポートについては、国全体の問題であり、政策による取組が期待される。
また、育休を取得した男性が、職場復帰した後も育児を続けられるように、働き方の見直しと業務効率化も必須となるだろう。2-2でみたように、現状で日本人男性の無償労働時間が短い背景には、そもそも有償労働時間が世界的に見て長い、という問題があるからである。
ここまで見てくると、企業が男性育休取得推進に必要なこととは、仕事の情報の共有やサポート体制、人事、ロールモデル構築、働き方や業務効率化など、女性活躍が必要としている要素と共通しているのである。
従って、男性育休を取得推進することは、直接的に、自社の女性社員の活躍推進にも役立つと言える。
逆に、現在の若年男性は育児休業取得や家庭との両立希望が強いのに、企業がこのようなことに取り組まなければ、若年男性の離職リスクが高まるだろう。
男性育休に関しては、近年、国の政策が急速に拡充されている。今年1月からは、中小企業を対象に、育休取得中の従業員の仕事を肩代わりした従業員に手当を支給した場合の助成金制度が新設された。
2025年度からは、育児・介護休業法や雇用保険法などの改正により、男性育休取得状況の公表義務が従業員300人以上の企業に拡大される他、夫婦いずれも、子の出生から一定期間内に14日以上の育休を取得すると、給付金によって、最大28日間は実質、手取りが100%保障される。
今後、さらに男性育休取得状況が量的にも質的にも水準が上昇していくか、推移に注目したい。
5――おわりに
企業が女性活躍施策を進めようとするときに、最も身近な壁は、実は社員の意識だと感じる人事担当者もいるのではないだろうか。男性からは「なぜ女性だけなのか」という不満の声、そして女性からは「家庭との両立だけで今でも忙しいのに、これ以上働けとない」という反発の声があることは、筆者も聞き及ぶところである。
しかし、女性活躍と同時に、男性社員の育休取得を推進し、中長期的には、社会の男女役割分業見直しや、ジェンダーギャップを進めていく、という方向性を示すことで、それらの反発を和らげられる可能性がある。
また、女性が活躍しやすく、男性が育休を取りやすい職場にするためには、本稿で説明してきたように、人事マネージメントや働き方の見直し、業務効率化などを進めることが必要となるため、結果的には、誰もが働きやすい職場になる。
長時間労働が当然だった時代に働き盛りを過ごした50~60代の男性には、男性社員が育休を取るということ自体、ピンと来ない人もいるかもしれないが、男性育休を進めることで、シニアにとっても働きやすい職場になると言える。
要は、男性も女性も、ライフステージを超えても、年齢を重ねても、「働きやすさ」と「働きがい」を感じられる職場環境を、どうやって構築していくかということである。
企業が「女性活躍」だけを追求しても、なかなか思うように進まないと事態が続いている中で、「男性育休」が突破口になることを期待したい。
(※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子)