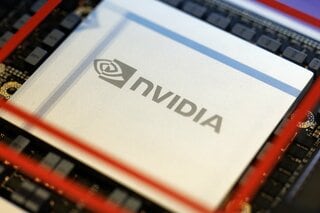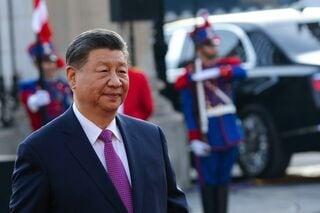日本では企業が「女性活躍」だけを追求してもなかなか進まない事態が続いている中で、「男性育休」が突破口になることを期待している。
1――はじめに
国内では、経済分野における女性の活躍がなかなか進まない。
厚生労働省によると、2023年度、10人以上規模の企業における女性管理職割合(課長相当職以上)は12.7%であり、過去10年でほとんど変わっていない(図表1)。
女性活躍は、近年、国内で多くの企業が取り組む「ダイバーシティ経営」の1丁目1番地であり、政府も女性活躍推進法施行などによって推進しているが、20年以上前に定めた「指導的地位に占める女性の割合が30%程度」という政府目標を達成する目途は、全く立っていない。
なぜ日本では、なかなか女性活躍が進まないのだろうか。
どうすれば、目標に近づくことができるのだろうか。
様々な課題が指摘されているが、筆者が重視しているのは、日本社会の中に文化として根付いてきた「家計(仕事)は夫、家庭(家事育児)は妻」という男女役割分業意識の見直しである。
固定的な男女役割分業意識の下では、家計責任が重い男性は、仕事優先で長時間労働になりがちで、家にいる間は休息以外の時間が取りづらい。
逆に家庭責任が重い妻は、家事育児を優先するため、非正規雇用で働いたり、正社員でも負担が軽い職務を選んだりしがちである。
それが職場でも「高度な職務は男性、負担の軽い職務は女性」という男女役割分業を形成することにつながり、結果的に、男女の昇進・昇給に格差が生じてきたことは、男女別賃金カーブを見ても明白である。
このように、家庭の男女役割分業と職場の男女役割分業は、縄のように絡み合っているのだ。
勿論、性別の分業体制がうまく機能している時代ならば、あまり問題は生じないかもしれないが、長寿化と未婚化が進んだ日本では、男女役割分業が固定したままでは、男女いずれにとってもリスクが生じていることを、筆者の既出レポートで指摘した。
また、日本企業の競争力強化やジェンダー平等のために女性活躍を進めようとするなら、根っこにある男女役割分業の見直しに取り掛からなければならない。と言っても、これは個人の価値観や家族関係に関わる問題でもあるため、個人単位や企業単位でアプローチしても、歯が立たないだろう。産業界全体、あるいは社会全体で取り組まなければならない問題だと言える。
このように述べると壁が高そうだが、実は筆者は、その“切り札”となり得るのが、男性の育児休業の取得促進だと考えている。
詳しくは後述するが、男性の育休取得を推進する主体は企業でありながら、男性社員の家庭での役割をプッシュするものであり、かつ職場の組織運営や組織風土の見直しにもつながると考えられるからだ。
前置きが長くなったが、このような視点に立って、本稿では、男性育休の役割について考察する。
まず、職場における女性活躍と家庭責任の関係について、昨年10月、定年後研究所とニッセイ基礎研究所が行った共同研究の結果を用いて説明し、その後、男性育休取得の現状と課題について整理する。そして、女性活躍を推進するために、男性育休取得推進が効果を発揮する可能性について論じる。