事件の翌年となる1996年4月、日米両政府は、普天間基地の全面返還に合意。時の総理が「5年ないし7年以内に」と明言した返還は、いまだ実現していない。
返還の条件となる移設工事は国の「代執行」によって進められ、その完成は2030年代半ば以降とされる。
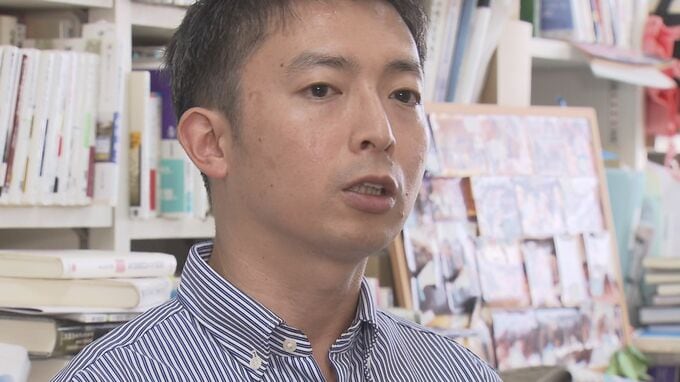
▼沖縄国際大学 野添文彬教授
「普天間基地を固定化させるのか、あるいは沖縄県内の辺野古に移設するか、という問題にすり替わった。この「二者択一」が、沖縄の基地負担の軽減の問題になってしまったということが、やはり大きな変化の一つ」
事件から今年で30年。野添教授は、今改めて「橋本談話」の検証が必要だと指摘する。橋本総理が1996年9月に発表した沖縄問題に関する談話は、次のようなものだ。

「私は、過ぐる大戦において沖縄県民が受けられた大きな犠牲と、沖縄県勢の実情、そして今日まで沖縄県民が耐えてこられた苦しみと負担の大きさを思うとき、私たちの努力が十分なものであったかについて謙虚に省みるとともに、沖縄の痛みを国民全体で分かち合うことがいかに大切であるかを痛感致しております」
日本全国で基地負担を「分かち合う」ということの意味は何だったのだろうか。野添教授は-。
「日本の政治家や官僚などがどこまで真剣に考えたのか、というのは、考えなければいけないと思います。どこまで近づいて、どこが擦り合わせられなかったのか。この30年間の沖縄問題を振り返る上でとても大事なことだと思いますし、これからの大きな問題を考えていく上でも大事」
高山朝光氏は、日米を動かした30年前の怒りは、今も沖縄の人々の心の中にあるという。

「もしも、万が一何か大々的なことが起きたら、県民の怒りが一挙に爆発するんじゃないかと。前のような勢いでね。米側としても日本政府としても、もう少し沖縄への配慮が大事だと思うんです」
◆ ◆ ◆
事件から30年たった今も、本質的な意味での「沖縄の基地負担軽減」や「地位協定の抜本的な見直し」は棚上げされたままだ。誕生したばかりの高市政権は沖縄とどう向き合うのか、その姿勢が問われている。








