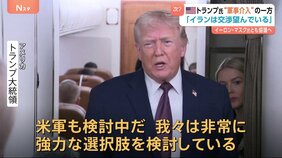生き残った女学生が綴った手記を読むと平静ではいられない。導かれるように宮沢はある場所へと向かった。
伊原第一外科壕跡、沖縄戦末期こうしたガマに住民や日本兵が隠れていた。
宮沢は集団自決に追い込まれた沖縄の人たちを思い浮かべた。一歩外に出ればサトウキビが静かに風に揺れていた。そのコントラストに衝撃を受けて創った歌が『島唄』だ。
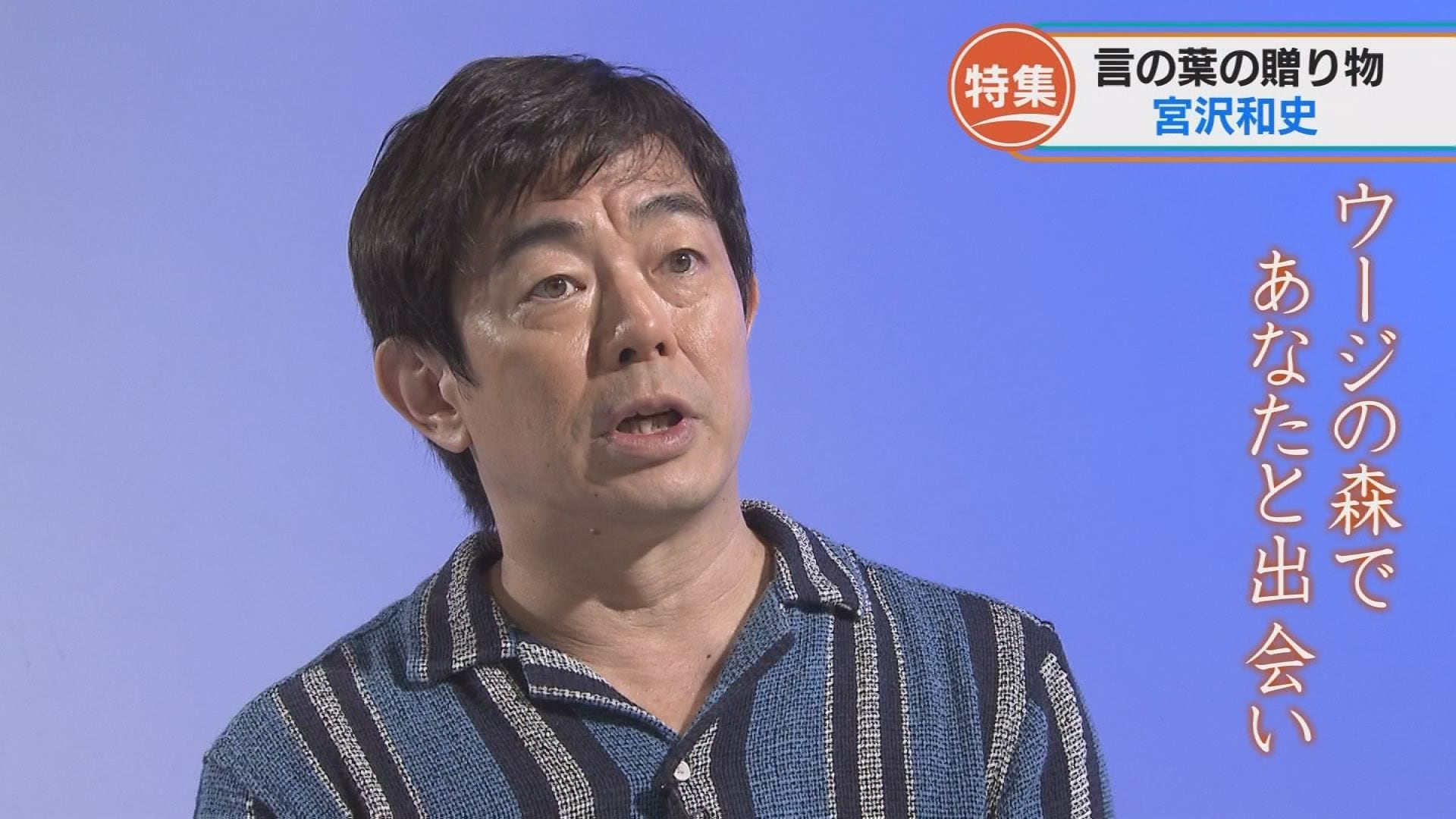
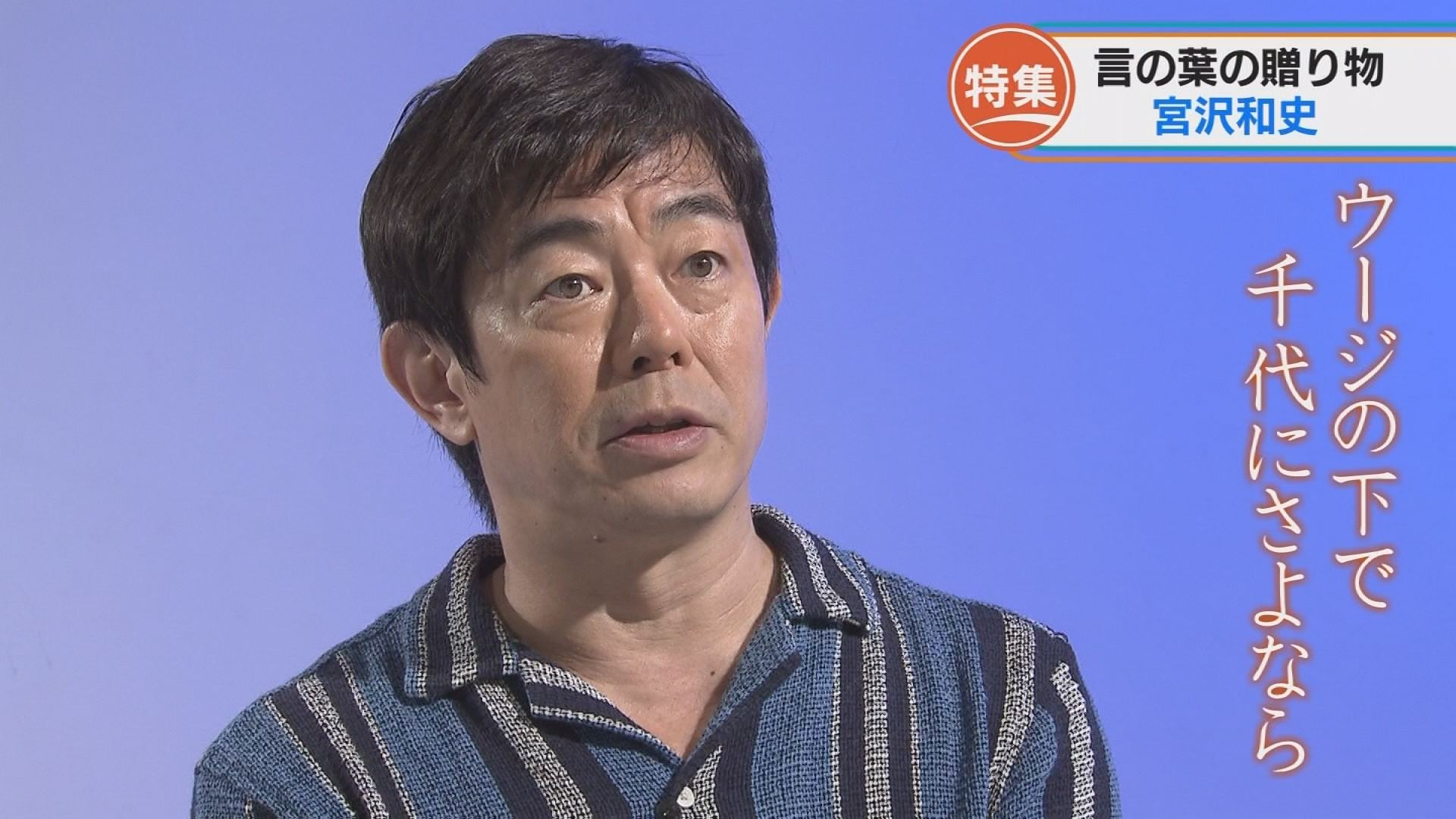
宮沢和史さん
『ウージの森であなたと出会い ウージの下で千代にさよなら』という詩にしたんですけど。サトウキビ畑で走りまわって遊んだ幼馴染であり恋人同士なのに、なんでサトウキビ畑の下で、「千代にさよなら」永遠にさよならしなければいけないのか。そこに琉球音階をつけるというのはあり得ないなと思いましてね。そこは西洋音階にして、ドレミファソラシドにして。そこは一旦三線を弾かないようにして」
『島唄』には、作曲、編曲における宮沢のメッセージがあった。
宮沢和史さん
「ウージの森であなたと出会い ウージの下で千代にさよなら」
こうして創られた『島唄』。当時、宮沢は様々な批判を受けた。
宮沢和史さん
「歌詞が薄っぺらいであるとか。琉球音階を使うとはなにごとだとか。こんなの『島唄』じゃないとか。そういう言葉をたくさん頂いて」
『島唄』を発売するか迷っていた時、宮沢はあるミュージシャンと出会い、言葉をかけられた。その『言の葉』が宮沢の迷いを断ち切った。
“魂までコピーしたらそれは真似じゃない”
『言の葉』を与えたミュージシャンは喜納昌吉だ。
宮沢和史さん
「相談してみよう、(喜納昌吉)さんに。どう思われますかって聞いたら、魂までコピーできたら、それは真似とは言わないんだ。この歌は沖縄を捉えていると。ぼくもそっちへ行くから、あんたこっちへ来てどんどん歌いなさいって、背中を押してくれたんですね。ほんと大きな言葉でしたね」

それから宮沢は沖縄と向き合い、深く関わり続けてきた。
“魂までコピーしたらそれは真似じゃない。”
『言の葉』に背中を押され、宮沢は今も『島唄』を歌い続け、メッセージを送っている。
宮沢和史さん
「戦争というものが本当になくなれば、そして沖縄の戦後がいよいよ終われば、平和を希求する歌は必要なくなりますから、『島唄』を歌う必要ががなくなるっていう。もうこの歌は歌いませんって言える未来が明日にでもきて欲しいって」