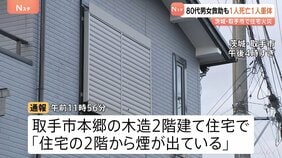那覇中心の沖縄を造り直す 解放基地に「悲願」の鉄道建設を構想
▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」
「かつて本島南部にあった鉄軌道に対する郷愁的感情論からはじまり、…観光客に特に西海岸の風光を紹介したい等々、少なからぬ希望を乗せての将来計画でもある」
沖縄にはかつて、鉄道が走っていた。1914年に、現在の那覇市と与那原町を結ぶ路線が、その後大正期までに、中部の嘉手納線、南部の糸満線と路線は拡張されたが、1945年の沖縄戦で破壊され、その後沖縄は鉄道のない島となっていた。
しかし、鉄道建設を思い描く記述からは、単なる再建要求ではなく、県土を再編成するうえで鉄道が果たす役割に大きな期待をかけていたことがうかがえる。
▽資料「軍用地および軍用施設~転用の基本的考え方~」
「(軍用地の)返還を機会に現在の機能麻痺に陥った那覇中心の都市を、新しいゾーニングの手法によって、中部の解放基地を中心として、新規に造成し直す新都市計画提案の有力な手段として鉄道建設を提唱する意見もある」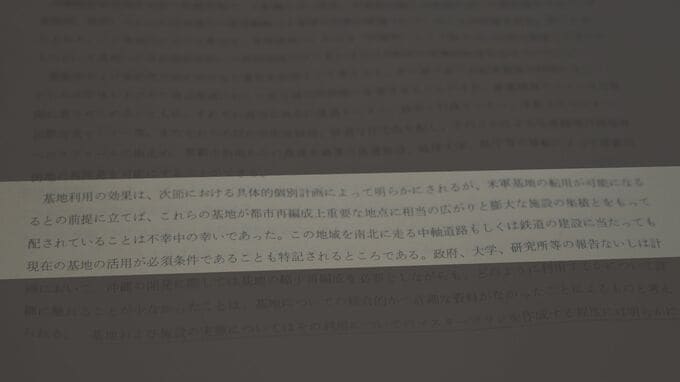
過密という問題の現実的解決策としても、鉄道建設が望まれた。当時の沖縄本島には、那覇から嘉手納までの南北約30km、西海岸から約5kmのエリアに人口の6割近く、46万2000人が集中していた。(1970年10月の国政調査)
この人口密度は、当時の大阪府よりは低いが京都市を上回り、本土の大都市並みであると記された。
経済復興にともなって自動車の保有台数も増加。1965年に4万1000台あまりだった自動車台数は1970年には11万4000台を超え、「1号線」と呼ばれた現在の国道58号の「交通混乱は驚くほど」だったという。鉄道による過密解消はまさに悲願だった。