今年8月、日向灘を震源とする地震を受けて、初めて発表された南海トラフ地震に関する「臨時情報」についてです。
国民の正しい理解や自治体の対応などさまざまな課題が浮き彫りとなる中、宮崎県庁で市町村の防災担当者が集まった研修会が開かれました。
研修会には、県内25の市町村の防災担当者が参加しました。
まず、午前中は沿岸の市と町が参加し、県の担当者や専門家が臨時情報の発表の流れや、自治体がとるべき防災対応などを説明。
このあと、8月に臨時情報が発表された際に浮き彫りとなった課題について意見交換しました。
(川南町の担当者)
「学校などの避難所を開くと、長期に渡る注意をしながら、普段の生活を継続するうえで開けられないというか、運用を制限される避難所もあるなと、8月8日の件で再認識した」
また、新富町は、「巨大地震警戒」が発表されたときの態勢を再検討をする必要性を感じたということです。
(新富町の担当者)
「巨大地震注意でこんなようでは、巨大地震警戒が出たときに、まさしく東の"半割れ"のときに、通常業務と臨時情報の対応、両面を迫られた中で職員の疲弊度を極小にしつつ、住民に対する避難の対応や来るかもしれないという後発地震への対応、これについて人的マンパワーが全く足りない」
また、研修会に参加した京都大学防災研究所宮崎観測所の山下裕亮助教は、臨時情報の発表時に、学校や海水浴場の運営などどのように対応するのかをあらかじめ公開しておくことも必要だと助言しました。
県は来週から、津波浸水想定区域内の住民を対象に、臨時情報の認知状況も盛り込んだ津波意識調査を実施し、今年度中に結果をまとめる予定です。
臨時情報への対応の難しさが改めて見受けられました。
8月の教訓を生かしつつ、民間との連携などさらに一歩進んだ議論も進める必要がありそうです。
全国のトップニュース
容疑者の男 事件前に4か所で放火 台北・無差別殺傷3人死亡11人重軽傷 現場には花を手向ける人の姿

高市総理 中央アジア5か国と初の首脳会談「共同宣言」採択 カスピ海ルートの円滑化を支援するなど

「本当にパニック」車が特急列車と衝突し炎上 車に乗っていた人が死亡 直前に踏切内で追突事故 近鉄京都線『新祝園駅』近くの踏切

山林に男性(89)の遺体 頭や手に外傷 クマに襲われたか 近くのイノシシ用わなに体長1.3メートルほどのクマ 宮城・大和町
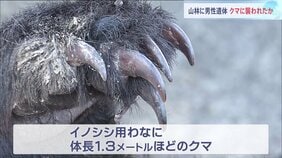
「お別れ」発表後はじめての週末 上野動物園前に長い列 パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」 予約なしでの観覧はあす(21日)が最終日

“アメリカ軍がシリア国内「イスラム国」の拠点を攻撃”トランプ政権発表 イスラム国の攻撃で米兵ら3人死亡への報復「今後も続ける」
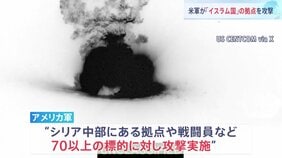
クリスマスから正月頃まで…ほぼ日本全域で12月24日頃~1月1日頃、この時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温になる可能性 気象庁が「高温に関する早期天候情報」発表

永住権獲得の新ビザ「トランプ・ゴールドカード」申し込み トランプ大統領「15億ドル以上集まった」 今月10日に受付開始
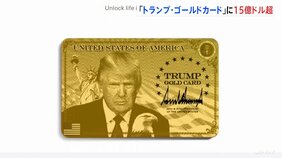
カテゴリ
Copyright © Miyazaki Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.