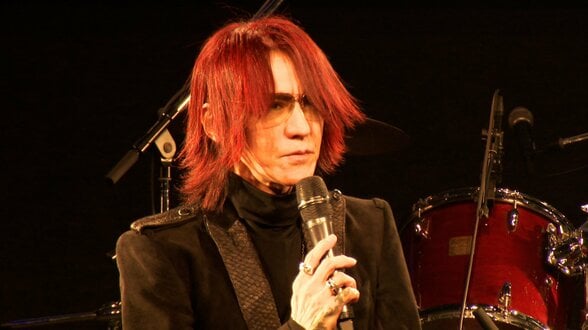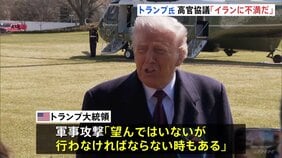高知県仁淀川町の『秋葉まつり』が3年ぶりに通常開催されました。人口減少に加え、新型コロナによって目前まで迫っていた「継承の危機」。「今年こそは」という思いを背負った人々が、祭りを未来につなげました。
愛媛県との県境に位置する仁淀川町別枝(べっし)地区。人口は100人あまりのこの地区が1年で一番賑わうのが毎年2月11日、秋葉まつりの日です。


秋葉まつりは土佐の三大祭りの一つとも言われています。氏神様をもともと祀られていた「市川家」に年に一度だけ帰し、ゆかりの地をめぐりながら再び秋葉神社に戻る祭りで200年以上の歴史があるとされています。去年とおととしは新型コロナの影響で規模を大幅に縮小。今年は3年ぶりの通常開催となりました。
(秋葉神社祭礼練り保存会 片岡和彦 会長)
「今日最後まで安全にやり遂げて次に繋げていく、その思いです。本当にみんな協力してここまで持ってきたなという思いが強い裏方もたくさんいるので、裏方の皆さんや関係者の皆さんに支えられて今日まで来たと感慨深い」

祭りでは、子どもたちが真剣を使った太刀踊りを披露します。少し緊張した様子で踊っているのは、小学5年生の藤野勝希(ふじの・しょうき)くん。3回目の参加。

今年は初めて参加する2人の弟が一緒で、「お兄ちゃん」として少しプレッシャーを感じています。母の茜さんも、息子たちを見守っていました。
(藤野茜さん)
「下の2人の弟が初めてなのでちょっとお兄ちゃんに期待というか、頑張っている姿を弟にも見せられたらなという思いも込めて『期待しとるよ』ということは言いました。すごく今日来るのが楽しみって言っていたので頑張ってくれると思います」
秋葉まつりの練りの行列が動き出しました。地区には、3年ぶりの通常開催を待ちわびた人たちが、大勢訪れました。

2年間の規模縮小では、子どもたちの太刀踊りや、一番の見どころ、鳥毛ひねりも中止されました。元々、地区の外から人を呼んで続けてきた秋葉まつり。2年の空白で、「祭りの継承」という課題がさらに大きなものとなっていました。

(見物客)
「今日がやれんかったら大変なことになるがやった」
練りの一行が到着した「大石家前(おおいしけまえ)」は、大勢の人で埋めつくされていました。ここで行われるのが、鳥毛ひねりです。

2人で、長さ7m、重さ5キロの「毛やり」を投げ合います。これも、脈々と受け継がれてきた技術です。今年、鳥毛役を担ったのは、中田英明(なかた・ひであき)さんと谷脇颯人(たにわき・はやと)さん。2人とも、子どもの頃から祭りに参加してきました。中田さんは、今年が初めての鳥毛役。谷脇さんは2回目です。

鳥毛役の先輩たちから、技術を教わります。
(中田英明さん)
「コロナになる前から次は自分っていうのが決まっていたので、2年間なくていよいよやらないかんという緊張と不安と」
(谷脇颯人さん)
「コロナになる前に1回やってその次が今回。プレッシャーというよりは、自分はこういう祭りとかが大好きなので楽しみの方が大きいほかの2つの集落に負けないようにという思いはあります」


出発からおよそ6時間後行列は秋葉神社に到着しました。

ご神体を乗せた神輿が本殿に入ろうとしますが祭りの終わりが惜しいと言わんばかりに何度も何度も拒まれます。

そしてついに…

弟たちと参加した、小学5年生の藤野勝希(ふじの・しょうき)くんも、無事に、最後まで踊りきることができました。
(Q.弟にかっこいい姿見せられた?)
「見せれてない」

こう話す勝希くんですが弟とお母さんの目にはちゃんと、かっこいい姿が映っていました。
(藤野光樹くん)
「(Q.お兄ちゃんの姿どうやった?)かっこよかった」
(藤野茜さん)
「今年は一緒に歩かせてもらったんですけど、やっぱり大人でもしんどいものを子どもでも衣装を着て竹とか刀とか持って一生懸命歩く姿を見て感動して泣きそうになってしまったんですけど、一番抱きしめるのが好きなのでよくやった言うて抱きしめてあげたい」
鳥毛ひねりを担当した2人は名残惜しい気持ちと達成感に満ち溢れていました。
(中田英明さん)
「楽しさの方が緊張より勝ったかな。お祭りで鳥毛やって歓声を聞いたら来年もやりたいなっていう気持ちにはなります」

(谷脇颯人さん)
「道中ずっと楽しみながらできたはできたんですけど、最後5投目投げた時に『終わったんか』という悲しい思いが出てきた。これまで土日とかもずっと練習してきたのでみんなと集まることももう1年ないのでそれで悲しい気持ちもでてきました」
(秋葉神社祭礼練り保存会 片岡和彦さん)
「やっと今年ここまでやることができたそれに尽きます。みんな今年はやろうぜという支えがあってこそ今このフィナーレを迎えようとしている、そういうことですね」
コロナ禍がもたらした、「継承の危機」を乗り越え、3年ぶりの“秋葉まつり”が幕を閉じました。「今年こそは」という人々の思いが、伝統を未来に繋ぎました。