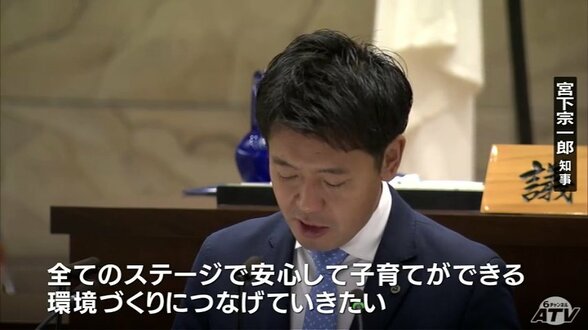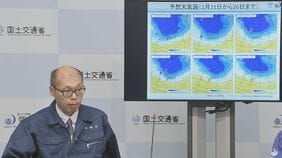「教育行政については基本的には教育委員会が担うことになります。今回のその人事の狙い。それからその他、諮問会議を設置するということも発表させていただいています。そうしたことについては、新教育長の就任の際、あるいはその前後の議会でのですね提案の際に、この狙いについてはしっかりと皆様に具体的な内容をもってご説明させていただきたいと思っています。以上です。」
Q.原子力関係で、最終処分地にしないとの国との約束というところで、国と具体的に今後、接触する機会というのはもうたっているものなんでしょうか?また当選してから電事連等から宮下知事の方に接触というのは、現時点であるものなのでしょうかというのをお聞きしたいと思います。
「これからですね、国と接触する機会というか、今日就任ですから。これから核燃料サイクル事業についてのあり方考え方、協議ということは進んでいくんだと思いますが、国との接触っていうことについてはこれからです。またご質問の2点目の電事連が当選してから今までの期間に接触があったかということでいけば、ございませんし、私からもアクションをとってございません。」
Q.ここの会見に至るまでの庁議などの場で、職員への挨拶でも仲間として受け入れてもらいたいということを宮下知事が強調されていたかと思うんですけれども、ここに込めた思い、職員へあえて伝えたという狙いというのがあれば教えてください。
「一緒に働く、同じ屋根の下で一緒に働く存在になるわけですから。何となくですね、今日感じているのは自分より結構職員の皆さんが緊張してるっていうのを感じてて、そういうことではなくて、そういうことではなくてっていうのもあれですけど、本当に1人の新しい職員が来たというつもりでですね、仲間として受け入れてほしいということでお伝えをさせていただいてますし。トップダウンとかボトムアップとかっていうふうなことをよく二項対立で皆さん考えたり書いたり伝えたりすることあると思うんですけど、今そういう時代じゃないと思うですよね。
やっぱり職員の皆さんとも対話をしながら、良い政策を作っていく時代だと思ってます。私も県民ですし、それから職員の皆さんも1人1人が県民ですので、1人1人が抱えている課題をしっかりとぶつけ合う環境ができれば、良い政策ができるということを、その仲間として受け入れてほしいという言葉に込めてお話をさせていただきました。」
Q.農林水産業について農業産出額が7年連続で3000億円を突破する一方で、農家さんからは所得が上がっている実感がないっていう声が聞かれていますが、それについて宮下知事はどのように応えていきたいでしょうか。
「まずそうした声は、選挙期間中もその活動期間中も多く聞かれています。本県が魅力ある農業を次世代に続いていく、次世代に繋いでいくためには、やはり所得の向上というのが一番大切ですから、その下支えする物価燃料高騰対策から始まって、本質的に農家の皆さんの所得が上がるような、あの政策対策をしっかりと各品目ごとに出していけるような形を、リンゴならリンゴ、米なら米、果物は果物っていうふうに、果物もいっぱいありますけどね。さくらんぼの時期ですから、さくらんぼならさくらんぼということで、野菜もありますけど、そういうふうな形をですね、作っていきたいなというふうには考えています。」
Q.何か品目ごとにその現状を把握するような部署の立ち上げなどは何か想定されている?
「あの部署の立ち上げ以前に私自身の対話をですね、その農家の皆さんと進めていきたいという思いはあります。ですから例えばリンゴ農家の皆さんとお話をさせていただく、米農家の皆さんと集まってお話をさせていただくというところからまずスタートしていきたいと思います。」
Q.経済界からその若者のUターンについて仕事作りが鍵になってくるんじゃないかという声が聞かれているんですが、それについてはどのようにお考えでしょうか?