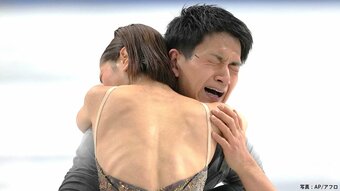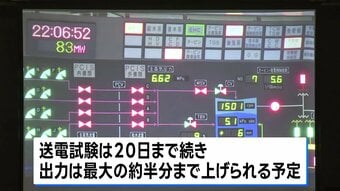■作業は光が届かず 作業後は「潜水病」の可能性も・・・飽和潜水”が内包する危険
井上キャスター:
作業船の中の巨大なカプセルが海中エレベーターになっていて、そこに3人くらいが入るんでしょうか?
遠山 常務理事:
通常複数でやるので、今回も3~4人の潜水員が作業をやると聞いています。
井上キャスター:
大人が3人入るとかなり狭い空間ですよね。
遠山 常務理事:
狭い空間に長期間閉じ込められるということで、精神的なタフさというのも相当要求されると思います。
井上キャスター:
作業時間に限度はないんですか。
遠山 常務理事:
“飽和”という意味なんですが、事前に13気圧まで体を慣らすということは13気圧の圧力を体にギュッとかけるということです。
炭酸飲料を想起していただければと思うんですが、炭酸飲料というのは圧力をかけて、シロップの中に炭酸ガスをたくさん封入するということです。ですから13気圧を人間の体にかけると、それだけガスがたくさん血液や細胞の中に溶け込むということになります。
13気圧の中で最大限溶け込ませる、“飽和”状態までガスを溶け込ませた状態で潜水をするということで、“飽和潜水”といわれるわけです。
飽和状態で作業をして、海底の気圧と同じ状態なので長期間作業ができるということですが、終わってから気圧を戻すことが非常に大事です。
炭酸飲料は蓋を開けるとシュワッと炭酸ガスが吹き出てきます。気圧がそれだけ少なくなったので、高気圧で溶け込んだガスが気圧が一気に下がったことによって気化してしまうわけです。
従って人間の体の中でも、高圧で封入されたガスが気圧が下がることによって一気に気化します。これは非常に危険な状態です。血管の中に空気ができる、あるいは血管が破裂したりするわけです。これは「潜水病」とか「減圧症」といわれてるのですが、それを起こさないように、潜水後1週間もかけてジワリジワリと元の1気圧に戻すという作業になります。非常に時間もかかるし危険を伴う作業になります。
作業中も海底は水温が低く、光が届かないほど暗い状況なので、非常に危険な状態で作業は続けられるといえると思います。
井上キャスター:
作業範囲が約15メートルだとすると、上から船でカプセルを動かせば作業範囲を広げられるということですか。
遠山 常務理事:
おそらくそうだと思います。何か危険があった場合にすぐレスキューができる体制を維持する必要がある、ということだと思います。