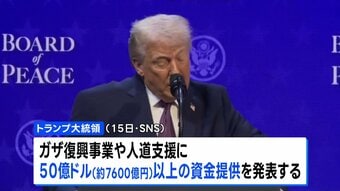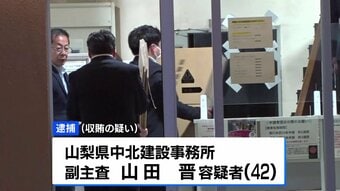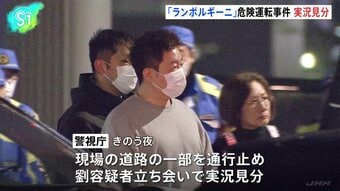米の増産「消費量を増やす方法はもっとあるはず」
――米の増産について「後戻りしそう」というお話がありました。新しい鈴木農水大臣が増産に後ろ向きな発言をするなど、石破内閣の方針を変えようという動きが出ています。政府の対応をどうみていますか?
米に限らず、穀物という商品は、多少の需給の変動で価格がものすごく乱高下するという特性を持っています。それは保存がきかないっていうことがあるんだけれども。「令和の米騒動」という人もいたが、今年なぜ価格が4000円以上になったのかを考えた時に、供給がギリギリでやっていることが底流にあるはずです。
世界ではどの国も農地を増やし、農業生産を増やしているのに、日本だけが耕作放棄地が増え、農業従事者が減っていく。日本だけがそういう政策をとり、カロリーベースの自給率が38%というのを、かなり異様だと思わない方がおかしいのではないでしょうか。
「作り過ぎたら価格が落ちるじゃないか」という反論は必ず出ますが、パリやニューヨークではおにぎり屋さんが長蛇の列です。プロダクトアウトではなく、マーケットインの形で米の需要ってもっとあるでしょう。国内でも、グルテンフリーのラーメンやパンなど、お米の消費量を増やす方法はもっとあるはずです。ご飯をもう一杯おかわりしましょうって話じゃなくて。
クマがたくさん出るようになったのは、あちこち耕作放棄地が増えたからだからね。だから、水源涵養とか、中山間地の保全やコストダウンなど、国の利益に資する形でお米を作った人が、価格が下がったことで継続できなくならないようにするのは、また別の政策です。それを直接所得補償っていう形にひとくくりにするから変なことになるんであって、どういう努力をした人に対して税金を使って所得を維持するのか、そういう細かい政策の集大成が農政なんです。
同性婚「ひとりひとりの権利の実現のために政府は努力すべき」
――選択的夫婦別姓の実現に向けて、自民党のなかで何が一番大きな障害になっているのでしょうか?(リスナーからの質問)
「絶対ダメ」という人がいるからです。「選択的であろうと何であろうと、夫婦別姓にすると家族が壊れる、家庭が壊れる」と。本当にそうですかね、というところはあるのですが、絶対そうだと言われちゃうと、話がそこから先に進まない。「選択的じゃないですか」と言っても「それはダメ」という方が一定数いらっしゃいました。
「親と子の名前が違うと郵便配達の人が困るのでは」という意見もありますが、外国ではちゃんと届いていますよね。とにかく「絶対ダメ」という理屈を展開される方が大勢いらっしゃって、党議拘束を外すかという議論もありましたが、自由民主党の一体性を保つために努力しようということで、結局まとまらなかったということです。
――同性婚についてはいかがですか? 来年にも最高裁で判断がなされそうです。
これは(同性婚に対して)好きとか嫌いとかいう話ではなく、私も当事者の方とある程度お話しさせていただいて、「それでないと自分は生きていけないんだ」というのはその人の権利なのでしょう。
「いや、自分はそういうの苦手だよね」っていう話とは別で、男性と男性が、女性と女性が、その人を配偶者として生きていかなければいけないという状況。あるいは、相続の問題など法的な問題と、その人の権利というものを両方勘案した時に、私は、好き嫌いの問題は別として、冷静に考えたときにひとりひとりの権利の実現のために政府は努力すべきじゃないかなと思っています。しかし、これまた「絶対ダメだ」という方は一定数いらっしゃいました。
――また議会でも、性的マイノリティへの理解増進や権利の拡充に対して、参政党のようにより批判的な議席も増えてますね。
一定数そういう方がいらっしゃるわけですから、そこにフォーカスして政策を訴えれば、そういう支持は得られるわけです。だけど、じゃあそういうことで全て決めていいですかと。
それによって個人の人権というものが妨げられてる人たちはどうするんですかという話も合わせてしないと、バランスは取れないでしょう。人権を単に多数決で決めていいのかと思いますね。
(後編に続く:石破前総理「保守はイデオロギーではない。保守の本質は寛容」いま振り返る在任1年と現政権の動き【インタビュー後編】)
(TBSラジオ『荻上チキ・Session』2025年11月13日放送「石破茂前総理がスタジオ生出演 政治とカネ、戦後80年所感…在任1年を問う」より)